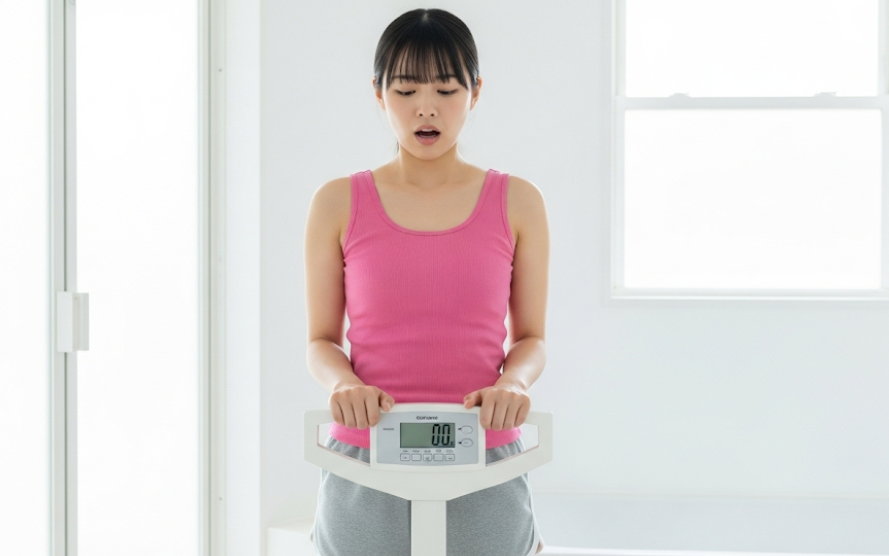)
こんにちは!鹿児島の不眠専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。最近よく眠れない上に、特にダイエットをしているわけでもないのに体重が急激に減ってきた、と感じてはいませんか。しっかり食べているつもりでも痩せると、何か悪い病気の初期症状ではないかと心配になるものです。
また、食欲不振を伴う場合や、もしかしたらうつ病が関係しているのかもしれない、と不安に思う方もいるでしょう。どれくらい体重が減少したら危険なサインなのか、そして具体的な対処法にはどのようなものがあるのか、様々な疑問が浮かんでくるかと思います。
この記事では、「不眠症と体重減少」という悩みを抱えるあなたに向けて、その原因からセルフチェックの方法、そして専門家への相談目安まで、網羅的に解説していきます。

睡眠不足が続くと、私たちの体内で食欲をコントロールしているホルモンのバランスが崩れ、体重が減少することがあります。これは、体に備わっている生理的な仕組みが正常に機能しなくなるためです。
私たちの体には、食欲を抑える「レプチン」というホルモンと、逆に食欲を高める「グレリン」というホルモンが存在します。十分な睡眠が取れている状態では、これらのホルモンが適切なバランスを保ち、食欲を正常に維持します。しかし、不眠によって睡眠時間が不足すると、レプチンの分泌が減少し、グレリンの分泌が増加する傾向があります。
このように言うと、「食欲が増すなら太るのでは?」と考えるかもしれません。確かに過食につながり体重が増加するケースもありますが、ホルモンバランスの乱れは自律神経の不調にもつながります。自律神経が乱れると、胃腸の働きが低下し、栄養の吸収効率が悪くなることがあります。その結果、食べているにもかかわらず、エネルギーが十分に吸収されずに体重が減少するという現象が起こり得るのです。
また、睡眠不足の状態は体にとって大きなストレスであり、常に体が緊張している状態になります。これにより基礎代謝が不必要に上がり、エネルギー消費量が増大して体重減少につながることも考えられます。

不眠症が引き起こす心身の不調は、直接的に食欲不振を招き、体重減少の大きな原因となることがあります。眠れないという状態は、精神的なストレスだけでなく、身体的な疲労も蓄積させます。
まず、精神的な側面から見ると、不眠が続くと日中の活動意欲や集中力が低下し、気分が落ち込みやすくなります。このような精神状態では、「何かを食べたい」という欲求自体が湧きにくくなります。食事は生命維持に不可欠な行為ですが、楽しむという側面も大きいため、気分の減退は食欲に直接影響を与えます。
次に、身体的な側面です。睡眠は、日中に受けた体のダメージを修復し、消化器官をはじめとする内臓を休ませるための重要な時間です。しかし、不眠によってこの休息時間が十分に確保されないと、消化器官の機能が低下します。胃もたれや便秘、下痢といった症状が現れやすくなり、食事を摂ること自体が苦痛に感じられるようになります。
これらの理由から、不眠症は「食べたいのに食べられない」「食べてもおいしく感じない」という食欲不振の状態を引き起こし、結果として摂取カロリーが不足して体重が減少していくのです。

不眠症と体重減少が同時に見られる場合、その背景に「うつ病」が隠れている可能性も考慮する必要があります。不眠はうつ病の代表的な症状の一つであり、両者は非常に密接に関連しています。
うつ病を発症すると、脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスが崩れます。これらの物質は、気分や意欲だけでなく、睡眠や食欲のコントロールにも深く関わっています。このため、うつ病の症状として、不眠(特に寝つきが悪い入眠障害や、朝早く目が覚める早朝覚醒)と、食欲不振が同時に現れることが少なくありません。
うつ病による食欲不振は、単に「お腹が空かない」というレベルにとどまらず、「食べ物の味がしない」「砂を噛んでいるようだ」と表現されるほど、食事への関心や喜びを完全に失ってしまうケースもあります。当然、食事量が減れば体重も減少します。
もし、不眠や体重減少に加えて、「何をしても楽しいと感じられない」「一日中気分が重い」「疲れやすくて何もする気になれない」といった症状が2週間以上続いている場合は、うつ病のサインかもしれません。不眠症の治療だけを行っても改善しない場合、うつ病という根本原因へのアプローチが不可欠です。

不眠と体重減少は、うつ病だけでなく、他の身体的な病気が原因で起こることもあります。特に注意したいのが、甲状腺の病気や消化器系の疾患です。
甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、全身の代謝が異常に活発になります。このため、常に体が興奮状態となり、動悸や多汗、手の震えといった症状とともに、夜眠れなくなる不眠症状が現れます。また、たくさん食べているにもかかわらず、エネルギー消費が激しいため、体重がどんどん減少していくのが特徴です。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍、慢性膵炎、炎症性腸疾患(クローン病など)といった病気があると、腹痛や消化不良によって食欲が低下したり、栄養の吸収がうまくいかなくなったりします。これらの症状が、結果として体重減少につながります。また、体の不快感や痛みがストレスとなり、不眠を引き起こすこともあります。
見過ごしてはならないのが、胃がんや大腸がんなどの悪性腫瘍の可能性です。がんは、初期段階では自覚症状が乏しいことが多いですが、進行すると原因不明の体重減少や食欲不振、倦怠感などが現れることがあります。
これらの病気は、早期に発見し、適切な治療を開始することが極めて大切です。単なる不眠や疲れのせいだと自己判断せず、他の身体症状がないかどうかも注意深く観察する必要があります。

意図的なダイエットをしていないにもかかわらず体重が減少する場合、それが危険なサインかどうかを判断するための一つの目安があります。一般的に、医療機関では「半年間で体重の5%以上の減少」を、医学的に意味のある体重減少と考え、精密な検査を推奨する基準としています。
これは、体重60kgの人であれば半年で3kg、体重50kgの人であれば2.5kgの減少に相当します。一見するとわずかな変化に思えるかもしれませんが、生活習慣を大きく変えていない中でのこの程度の減少は、体の中で何らかの異常が起きている可能性を示唆します。
| もとの体重 | 5%の減少量(半年間での目安) |
| 50 kg | 2.5 kg |
| 60 kg | 3.0 kg |
| 70 kg | 3.5 kg |
| 80 kg | 4.0 kg |
さらに、体重減少の割合が10%(半年で60kgの人が6kg減る)を超えると、より緊急性が高い状態と判断されます。20%以上の減少では、栄養障害や多臓器への影響が出ている可能性が高く、速やかな医療介入が必要です。
ただし、これらの数値はあくまで目安です。5%に満たない減少であっても、不眠の他にも倦怠感や微熱、痛み、食欲不振など、他の自覚症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診することが賢明です。

体重減少において、その「量」だけでなく「速度」も非常に重要な判断材料となります。半年で5%という目安に加えて、より短期間での急激な体重の変化は、体が発する危険信号である可能性が高まります。
例えば、1ヶ月で体重の2%以上(体重60kgの人で1.2kg以上)が減少するようなケースは、注意深く経過を観察する必要があります。生活習慣の変化や一時的なストレスなど、思い当たる原因がないにもかかわらず、体重計の目盛りが明らかに減り続けている状態は、体に何らかの負担がかかっているサインです。
急激な体重減少は、体がエネルギー不足の状態に陥っていることを意味します。この状態が続くと、筋肉量が低下して体力が落ちるだけでなく、免疫力も低下し、感染症にかかりやすくなるなど、さらなる健康問題を引き起こすリスクがあります。
「最近、ズボンが緩くなった」「ベルトの穴が一つずれた」といった日常のささいな変化が、重要な手がかりになることもあります。体重を毎日測定する習慣がない方も、もし不眠とともに体調の変化を感じたら、一度体重を測ってみることをお勧めします。そして、その数値の変化を記録しておくことが、後の診断の際に役立つ情報となります。

不眠症と体重減少に悩んでいる場合、専門医に相談する前に、まずは自分自身で試せるセルフケアや対処法を実践してみることが大切です。特に、ストレスが原因となっているケースでは、生活を見直すだけで症状が和らぐことがあります。
現代社会においてストレスを完全になくすことは困難ですが、上手に付き合っていく工夫はできます。自分が何にストレスを感じているのかを把握し、それに対する解消法を見つけることが鍵となります。例えば、趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したりするだけでも気分転換になります。また、自然の中を散歩したり、軽い運動を取り入れたりするのも効果的です。
心身の緊張を解きほぐすためには、意識的にリラックスする時間を作ることが有効です。就寝前にぬるめのお湯にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、アロマテラピーを取り入れるなど、自分が心地よいと感じる方法を試してみましょう。特に深呼吸や瞑想は、場所を選ばずに手軽にでき、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。
東洋医学の観点から、鍼灸治療も選択肢の一つです。鍼灸は、自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせる効果が期待できます。特に、不眠に効果的とされる「神門(しんもん)」や「失眠(しつみん)」といったツボへの刺激は、睡眠の質を高める助けとなる場合があります。ただし、治療を受ける際は、必ず国家資格を持つ信頼できる鍼灸師に相談してください。
これらのセルフケアは、症状の根本的な解決に至らない場合もありますが、心身の状態を整え、医療機関での治療効果を高める土台作りにもなります。

自身の状態を客観的に把握するために、セルフチェックを行うことは非常に有効です。不眠症やうつ病の可能性について、簡単なチェックリストを用いて確認してみましょう。
以下の項目について、過去1ヶ月間に週3回以上の頻度で当てはまるものがあるか確認してみてください。
当てはまる項目が多いほど、不眠症の可能性が考えられます。
不眠に加えて、以下のような心の状態や身体の変化がないか振り返ってみましょう。これは、うつ病の診断基準(QIDS-J)を簡略化したものです。
これらの症状、特に「気分の落ち込み」や「興味・喜びの喪失」を含む複数の項目が2週間以上続いている場合は、専門家への相談を検討すべきサインです。

不眠症を改善し、健康的な体重を取り戻すためには、日々の生活習慣を見直すことが基本となります。特に「睡眠」「食事」「運動」の3つの柱を整えることが、睡眠の質を向上させる鍵です。
質の高い睡眠のためには、快適な環境が不可欠です。まず、寝室は静かで、光が遮られた暗い状態を保ちましょう。温度や湿度も、自分が快適だと感じるレベルに調整します。また、体に合った寝具を選ぶことも大切です。就寝1〜2時間前にはスマートフォンやパソコンの使用を控え、脳への刺激を減らすことも有効な対策です。
規則正しい時間に、バランスの取れた食事を摂ることを心がけましょう。特に、睡眠の質を高める効果が期待されるアミノ酸「トリプトファン」を多く含む食品(乳製品、大豆製品、バナナなど)を意識して摂るのも良い方法です。逆に、就寝前のカフェインやアルコールの摂取は、眠りを浅くする原因となるため避けるべきです。食事は少量でも良いので、栄養価の高いものを選びましょう。
日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなります。ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど、無理なく続けられるものから始めましょう。ただし、就寝直前の激しい運動は体を興奮させてしまうため、逆効果になる可能性があります。運動は、就寝の3時間前までには終えるのが理想的です。

セルフケアや生活習慣の改善を試みても、不眠や体重減少が2週間以上続く場合は、専門の医療機関への相談を強く推奨します。自己判断で放置してしまうと、背景にある病気が進行してしまう恐れがあります。
まず、どの科を受診すればよいか迷う場合は、かかりつけの内科医に相談するのが第一歩です。身体的な病気がないかを全般的に調べてもらうことができます。問診や血液検査などを通して、甲状腺の病気や消化器系の疾患、その他の内科的疾患の可能性をスクリーニングしてもらえます。
内科的な検査で特に異常が見つからず、ストレスや精神的な問題が原因として強く疑われる場合は、心療内科や精神科が専門となります。これらの科では、不眠やうつ病に対する専門的なカウンセリングや薬物療法を受けることが可能です。
また、不眠の症状そのものに特化した治療を受けたい場合は、「睡眠外来」という専門外来も選択肢となります。ここでは、睡眠に関する多角的な検査(睡眠ポリグラフ検査など)を行い、より正確な診断と個人に合った治療法の提案が受けられます。
大切なのは、「たかが不眠」と軽視せず、体のサインに耳を傾けることです。早めに専門家の助けを借りることが、早期回復への一番の近道となります。
この記事では、不眠症と体重減少の関係について、その原因から対処法、そして医療機関を受診する目安までを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
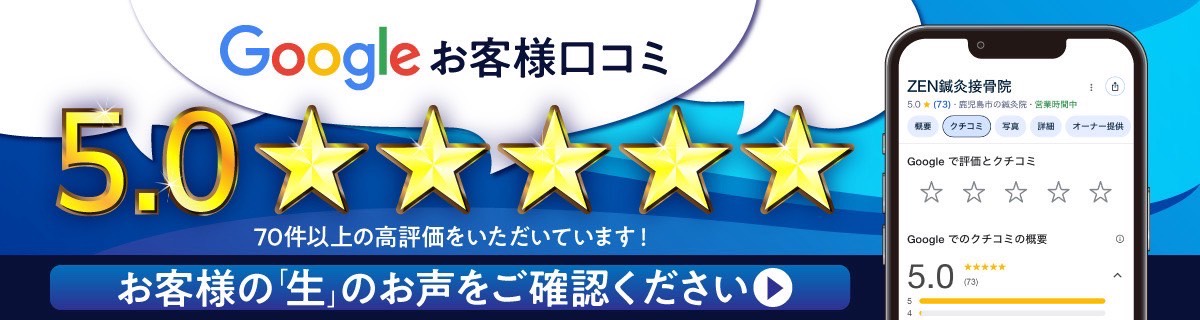


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。