)
こんにちは!鹿児島の不眠専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。不眠が続いて仕事に集中できないとき、「不眠症で傷病手当を受けながら休めないだろうか」と考える方は少なくありません。実際に不眠症でも休職できるのか、休んだ場合に仕事でクビになるのではないかという不安、休職期間やその間の給料の問題など、悩みは尽きないでしょう。
こうした状況で頼りになるのが公的な支援制度ですが、手続きには心療内科などで発行される診断書が必要です。この記事では、これらの悩みを解消し、症状改善の一助となる鍼灸治療の可能性にも触れながら、不眠症の方が安心して療養に専念するための情報を詳しく解説します。

不眠症を理由に会社を休職することは、多くの場合において可能です。
不眠症は、単なる寝不足ではなく、日中の活動に支障をきたす医学的な治療を要する状態です。そのため、業務遂行が困難であると医師が判断し、会社がそれを認めれば、病気やケガを理由とする「私傷病休職」の制度を利用できます。
ここで大切なのは、「休職」と「欠勤」の違いを理解しておくことです。欠勤は、労働の義務があるにもかかわらず自己都合で休むことを指しますが、休職は会社の許可を得て正式に労働義務が免除される状態を指します。
したがって、不眠症の症状がつらく、仕事への影響が出ていると感じたら、まずは会社の就業規則を確認し、休職制度の有無や条件を把握することから始めると良いでしょう。

不眠症で休職を検討する場合、相談先として適切なのは心療内科や精神科といった専門の医療機関です。
なぜなら、傷病手当金の申請や休職手続きには、専門医による客観的な診断が不可欠だからです。一般的な内科でも睡眠薬の処方は可能ですが、不眠の背景にあるストレスや精神的な要因まで踏み込んで診断し、休職の必要性を判断してもらうには、専門医の知見が求められます。
クリニックでは、医師があなたの症状や生活状況、仕事でのストレスなどを丁寧にヒアリングし、休職が適切かどうかを判断します。初診ですぐに診断書が発行されるとは限りませんが、継続的な通院を通じて、あなたの状態を正確に把握した上で必要な書類を作成してくれます。
休職をスムーズに進めるためにも、まずは勇気を出して専門医のいるクリニックの扉を叩くことが、回復への第一歩と考えられます。
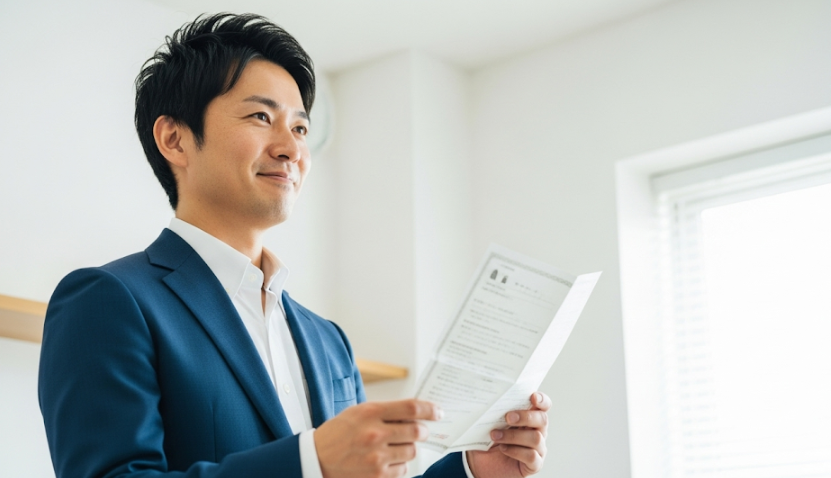
休職手続きを進める上で、医師が作成する「診断書」は絶対に欠かせない書類です。
この診断書は、あなたが「病気やケガによって就労が困難な状態にある」ことを会社に対して客観的に証明する公的な書類となります。これがあることで、会社はあなたの健康状態を正確に把握し、休職を正式に認めることができます。
診断書を入手する具体的な流れは以下の通りです。まず心療内科や精神科を受診し、医師に現在のつらい症状や仕事に支障が出ている状況を詳しく伝えます。その上で、「休職を考えており、会社に提出するための診断書が必要です」と明確に依頼してください。
診断書には通常、病名(例:不眠症、睡眠障害)、症状、そして「約〇ヶ月の休養を要する」といった具体的な休職期間が記載されます。なお、診断書の発行には費用がかかるため、事前に確認しておくと安心です。

傷病手当金は、誰もが自動的に受け取れるわけではなく、以下の4つの条件を全て満たす必要があります。
傷病手当金の対象となるのは、仕事中や通勤中以外の、つまりプライベートな時間で発生した病気やケガの治療のための休業です。不眠症は通常、業務外の事由と見なされるため、この条件に該当します。もし業務が原因で精神疾患を発症した場合は、労働災害保険(労災)の対象となる可能性があります。
医師の診断に基づき、「これまで従事していた業務を遂行できない」と判断されることが必要です。これは自己判断ではなく、医師の意見書を基に、加入している健康保険組合などが最終的に判断します。
仕事を連続して3日間休んだ期間(これを「待期期間」と呼びます)が完成し、4日目以降も休業している場合に、その4日目から支給が開始されます。この待期期間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。
傷病手当金は生活保障を目的とするため、休業期間中に会社から給与が支払われている場合は支給されません。ただし、支払われる給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額分が支給されます。

休職期間中は、原則として会社から給料は支払われません。この収入が途絶える期間の生活を支えるために設けられているのが、傷病手当金制度です。
傷病手当金として支給される金額は、おおよそ「給与の3分の2」が目安となります。具体的には、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2が1日あたりの支給額です。
ただし、いくつか注意点があります。一つは、申請してから実際に振り込まれるまでには、1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかる場合があることです。そのため、休職に入る前にある程度の生活費を準備しておくと、精神的な余裕を持って療養に専念できます。
また、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)の支払いは、休職中も継続して必要になります。給与からの天引きがなくなるため、会社と支払い方法について事前に相談しておくことが大切です。
病気を理由に正規の手続きを踏んで休職した場合、その休職期間中に解雇される(クビになる)可能性は極めて低いです。
日本の労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされています。医師の診断に基づき、会社の制度に則って休職している従業員を解雇することは、この「不当解雇」にあたる可能性が高いと言えます。
しかし、注意すべき点も存在します。それは、会社の就業規則で定められている休職期間の上限です。多くの会社では、「勤続年数に応じて最長〇年まで」といった形で休職できる期間が決められています。この期間を満了しても復職が困難であると判断された場合、自然退職や解雇扱いとなる規定が設けられていることが一般的です。
したがって、休職に入る前に、ご自身の会社の就業規則を必ず確認し、休職可能な期間や復職に関するルールを正確に把握しておくことが、将来の不安を減らす上で鍵となります。

傷病手当金が支給される期間は、支給が始まった日から「通算して最長1年6ヶ月」です。
ここで重要なのが「通算して」という点です。これは、以前の制度からの大きな変更点であり、利用者にとってはメリットの大きい改正と言えます。
具体的には、1年6ヶ月の期間内であれば、途中で一度復職し、その後再び同じ病気やケガで休業した場合でも、残りの期間分の傷病手当金を受け取ることができます。例えば、3ヶ月間受給した後に半年間復職し、再度休職した場合、残りの1年3ヶ月分の支給枠が利用可能です。
この制度により、体調を見ながら段階的に職場復帰を目指すなど、より柔軟な療養計画を立てやすくなりました。ただし、支給期間の起算日はあくまで「最初に支給が開始された日」であるため、その日から1年6ヶ月という大きな枠の中で管理されることを覚えておきましょう。

不眠症を含む精神疾患の治療には、傷病手当金以外にも利用を検討できる公的な支援制度があります。経済的な負担を軽減し、治療に専念するために、これらの制度についても知っておくと良いでしょう。
| 制度名 | 内容 |
| 自立支援医療制度(精神通院医療) | 精神疾患の治療のために、指定の医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担額が、通常3割のところを原則1割に軽減される制度です。所得に応じて月額の自己負担上限額も設定されます。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある場合に交付される手帳です。税金の控除や公共料金の割引など、様々な福祉サービスを受けることができます。 |
自立支援医療制度は、通院治療を継続する上での経済的負担を直接的に軽くするものです。一方、精神障害者保健福祉手帳は、より広範な生活支援を受けるための基盤となります。
どちらの制度も、申請には医師の診断書が必要となります。主治医や市区町村の障害福祉担当窓口、または病院のソーシャルワーカーなどに相談し、ご自身の状況に合わせて活用を検討することをおすすめします。

薬物治療に抵抗がある方や、薬の効果が十分でない場合に、選択肢の一つとして考えられるのが鍼灸治療です。
東洋医学に基づく鍼灸は、心と体のバランスを整えることを目的としています。不眠症の多くは、ストレスや疲労によって自律神経のバランスが乱れ、体を興奮させる交感神経が夜間も優位になってしまうことが原因と考えられています。
鍼灸治療では、特定のツボを刺激することで、心身をリラックスさせる副交感神経の働きを高め、自然な眠りに入りやすい状態へと導きます。血行を促進し、首や肩の緊張を和らげる効果も期待できるため、心身の緊張からくる不眠には特に有効と考えられます。
薬物治療のように即効性があるわけではありませんが、副作用の心配が少なく、体質そのものを改善していくアプローチである点が大きなメリットです。定期的な施術を続けることで、睡眠の質が向上し、日中のだるさや気分の落ち込みが改善していくケースも少なくありません。主治医に相談の上、西洋医学と並行して試してみる価値のある選択肢と言えるでしょう。

休職期間は、治療に専念し、心身を回復させるための貴重な時間です。この期間を有効に過ごすことが、スムーズな復職につながります。
まずは、焦らずにゆっくりと休むことが最も大切です。特に休職初期は、仕事のことは一旦忘れ、心と体を休ませることに集中してください。
生活リズムを整えることも、不眠の改善には不可欠です。毎日決まった時間に起床し、朝日を浴びるように心がけましょう。日中は、ウォーキングなどの軽い運動を取り入れると、夜の寝つきが良くなる助けとなります。医師の指示に従い、定期的な通院を欠かさず、処方された薬があれば正しく服用することも重要です。
休職期間中は、自己判断で薬を中断したり、昼夜逆転の生活を送ったりすることは避けるべきです。また、将来への不安から、転職や退職といった大きな決断を急ぐのも良くありません。心身が健康な状態に戻ってから、改めて考えるようにしましょう。
会社との連絡を完全に絶ってしまうのも望ましくありません。月に一度程度、人事担当者などに状況を簡単に報告することで、会社側も安心し、復職に向けた協力体制を築きやすくなります。罪悪感を感じる必要はありません。休職は、回復して再び活躍するための必要なステップと捉えましょう。
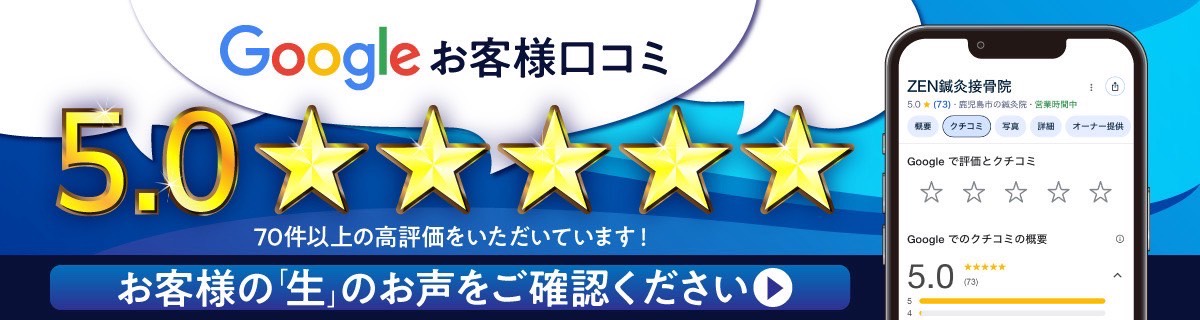


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。