)
こんにちは!鹿児島の不眠専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。「最近よく眠れない…これって不眠症なのかな」「病院に行くべきか迷うけど、もし行くなら何科がいいんだろう?」このような悩みを抱えていませんか。睡眠に関する問題は、日常生活に大きな影響を与えるため、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが大切です。しかし、いざ病院を考えたとき、どのタイミングで、どの診療科を選ぶべきか判断に迷う方は少なくありません。
睡眠障害の背後には、ストレスから身体の不調まで様々な原因が隠れていることがあります。例えば、身近なかかりつけ医や内科で相談することも一つの手ですし、睡眠薬の処方を希望する場合もあるでしょう。一方で、西洋医学だけでなく鍼灸院での治療という選択肢も存在します。この記事では、不眠症で何科にいけばいいかという疑問に対し、あなたの症状や状況に合わせた最適な病院選びのポイントを分かりやすく解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

夜になってもなかなか寝付けない、眠りが浅くて何度も目が覚める、といった経験は誰にでもあるかもしれません。しかし、このような状態が長く続き、日中の活動にまで影響が出ている場合、それは単なる寝不足ではなく「睡眠障害」の可能性があります。
睡眠障害にはいくつかのタイプが存在します。
これらの症状が週に3日以上あり、3ヶ月以上にわたって続く場合、医学的には「慢性不眠症」と診断されることがあります。不眠は国民病とも言われ、決して珍しい症状ではありません。そのため、「自分だけがおかしいのではないか」と過度に心配する必要はありませんが、生活の質を著しく低下させる要因となるため、放置せずに適切な対応を考えることが大切です。

眠れない日が数日続いただけでは、すぐに病院へ行くべきか迷うことでしょう。一時的な不眠は、大きなイベント前の緊張や環境の変化など、誰にでも起こり得ます。
しかし、受診を検討すべき明確な目安がいくつか存在します。
第一に、不眠の症状が2週間以上続いている場合です。一過性の不眠であれば、原因が解消されると自然に改善することが多いですが、症状が長引く場合は背景に何らかの問題が隠れている可能性が考えられます。
第二に、日常生活に具体的な支障が出始めたときです。例えば、日中に強い眠気に襲われて仕事や勉強に集中できない、気力が湧かず活動意欲が低下している、注意力が散漫になってミスが増えた、といった状態は受診を考えるべきサインと言えます。睡眠不足は、単に眠いというだけでなく、認知機能や判断力の低下を引き起こすため、放置すると事故などにつながるリスクも否定できません。
これらの点を踏まえると、不眠が「一時的なもの」から「生活の妨げになるもの」へと変わった時点が、専門家への相談を始める適切なタイミングと考えられます。

「何科に行けばいいか全く見当がつかない」という場合、最も身近で頼りになるのが、普段からあなたの健康状態を把握してくれている「かかりつけ医」です。特に内科のかかりつけ医がいる場合は、最初の相談相手として非常に適しています。
かかりつけ医に相談する大きなメリットは、総合的な視点から診察してもらえる点にあります。あなたの既往歴や普段の生活習慣、服用している薬などを踏まえた上で、不眠の原因がどこにあるのかを一緒に考えてくれます。
例えば、不眠の原因が生活習慣の乱れにあると判断されれば、睡眠衛生に関する具体的な指導を受けられるでしょう。また、もし身体的な病気が疑われる場合は、その場で必要な検査を行ったり、より専門的な診療科を紹介してもらえたりします。精神的なストレスが強いと判断された場合でも、心療内科や精神科への受診をスムーズに繋いでくれるため、自分で一から病院を探す手間が省けます。
このように、どのドアを叩けばよいか分からないという状況において、かかりつけ医は最適な水先案内人の役割を果たしてくれます。まずは一度、気軽に相談してみることから始めるのが良いでしょう。

不眠の症状と共に、何か身体的な不調を感じている場合は、まず内科を受診することを検討してください。眠れない原因が、身体に隠れた病気である可能性も少なくないからです。
例えば、以下のような症状がある場合は内科が適しています。
特に、甲状腺機能の異常(亢進症または低下症)や、更年期に伴うホルモンバランスの乱れなどは、不眠を引き起こす代表的な身体的要因です。これらの疾患は血液検査などで診断がつくことが多く、原因となっている病気の治療を行うことで、不眠の症状が劇的に改善する場合があります。
呼吸器内科や循環器内科、あるいは女性であれば婦人科、甲状腺の異常が疑われるなら内分泌内科といった、より専門的な内科を受診するのも一つの方法です。身体的な原因が解消されない限り、睡眠薬を飲んでも根本的な解決には至らないため、まずは内科で身体全体のチェックをしてもらうことが解決への近道となる場合があります。

仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、将来への不安など、はっきりとした精神的ストレスが原因で眠れないと感じている場合は、精神科や心療内科が専門となります。
これら二つの診療科は似ていますが、少し違いがあります。
どちらを受診すべきか厳密に区別する必要はありません。多くのクリニックでは両方の領域をカバーしており、医師が診察の上で適切なアプローチを判断してくれます。
これらの診療科では、カウンセリングを通じてストレスの原因を探ったり、物事の捉え方や考え方の癖を修正する認知行動療法を行ったりします。また、必要に応じて睡眠導入剤や抗うつ薬、抗不安薬などを処方し、つらい症状を和らげる手助けをしてくれます。心の負担が軽くなることで、自然な眠りを取り戻せるようになることは少なくありません。

不眠の治療法として「睡眠薬」を思い浮かべる方は多いでしょう。睡眠薬は、内科、精神科、心療内科など、多くの診療科で処方してもらうことが可能です。つらい不眠症状を一時的に緩和し、心身を休ませる上で非常に有効な手段となります。
ただ、睡眠薬の使用にはいくつかの注意点も伴います。
第一に、依存性の問題です。長期間にわたって漫然と使用を続けると、薬なしでは眠れないと感じるようになったり、効果が薄れてより多くの量が必要になったりすることがあります。
第二に、副作用の可能性です。薬の種類によっては、翌朝に眠気やふらつきが残る「持ち越し効果」や、一時的に記憶がなくなる「健忘」といった副作用が現れることがあります。
これらの理由から、睡眠薬の処方を受ける際は、医師の指示を厳格に守ることが何よりも大切です。自己判断で量を増やしたり、急に中断したりすることは絶対に避けてください。特に精神科や心療内科では、依存性の少ない新しいタイプの薬を選択したり、患者一人ひとりの不眠のタイプ(入眠困難、中途覚醒など)に合わせて作用時間の異なる薬を使い分けたりするなど、より専門的な知識に基づいた処方を行ってくれます。
薬はあくまで補助的な手段と捉え、根本原因の解決に向けた生活習慣の改善などと並行して治療を進める視点が鍵となります。

ここまで様々な診療科を紹介してきましたが、それでも「自分はどこが最適なのか」と迷うかもしれません。ここでは、診療科を選ぶ上での判断ポイントを改めて整理します。
以下の表は、主な症状や原因と、それに対応する推奨される診療科をまとめたものです。自分の状態に最も近いものから、受診先を検討してみてください。
| 主な症状・原因 | 推奨される診療科 | 特徴 |
|---|---|---|
| 何科に行けばいいか分からない、まずは相談したい | かかりつけ医 | 全体的な健康状態を把握しており、適切な専門科への紹介もスムーズ。 |
| 動悸、息切れ、頻尿、いびき、むずむず脚など、身体の不調を伴う | 内科(呼吸器、循環器、内分泌など)、婦人科 | 身体的な疾患が不眠の原因になっていないかを検査・治療する。 |
| 仕事や家庭のストレス、気分の落ち込み、強い不安感が原因 | 精神科、心療内科 | カウンセリングや薬物療法を通じて、心の不調からくる不眠を治療する。 |
| 日中に耐えがたい眠気がある、夢遊病のような行動があるなど、特殊な睡眠の問題がある場合 | 睡眠専門外来、脳神経内科 | 精密検査(終夜睡眠ポリグラフ検査など)を行い、ナルコレプシーやレム睡眠行動障害などの特殊な睡眠障害を診断する。 |
| 歯ぎしりがひどい | 歯科、口腔外科 | マウスピースの作成などで歯ぎしりを軽減し、睡眠の質の向上を目指す。 |
重要なのは、一つの症状だけで判断するのではなく、自分の全体的な心身の状態を考慮することです。例えば、ストレスも感じるし、いびきも大きいという場合は、まずはいびきの専門である呼吸器内科や耳鼻咽喉科を受診し、それでも改善しなければ心療内科を検討する、といった段階的なアプローチも有効です。

「睡眠」に関する問題をより専門的に、かつ集中的に解決したい場合は、「睡眠外来」や「睡眠医療センター」といった専門機関を受診するのが最も確実な方法です。
睡眠外来は、その名の通り睡眠障害全般を専門的に扱う診療科です。ここには、日本睡眠学会が認定する「睡眠専門医」が在籍していることが多く、不眠症だけでなく、睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー、むずむず脚症候群、レム睡眠行動障害といった、あらゆる睡眠関連疾患の診断と治療に対応しています。
睡眠外来の大きな特徴は、精密な検査体制が整っている点です。代表的なものに「終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査」があります。これは、一晩病院に宿泊し、脳波や心電図、呼吸の状態、筋肉の動きなどを詳細に記録する検査で、不眠の質や隠れた病気の有無を客観的に評価することができます。
また、内科、精神科、耳鼻咽喉科、歯科など、関連する他の診療科と緊密に連携している施設が多いのも強みです。これにより、一人の患者に対して多角的なアプローチが可能となり、より根本的な原因に迫った治療計画を立てることができます。どの診療科に行っても症状が改善しなかった方や、自分の症状の原因を徹底的に突き止めたい方は、睡眠外来への相談を強くお勧めします。
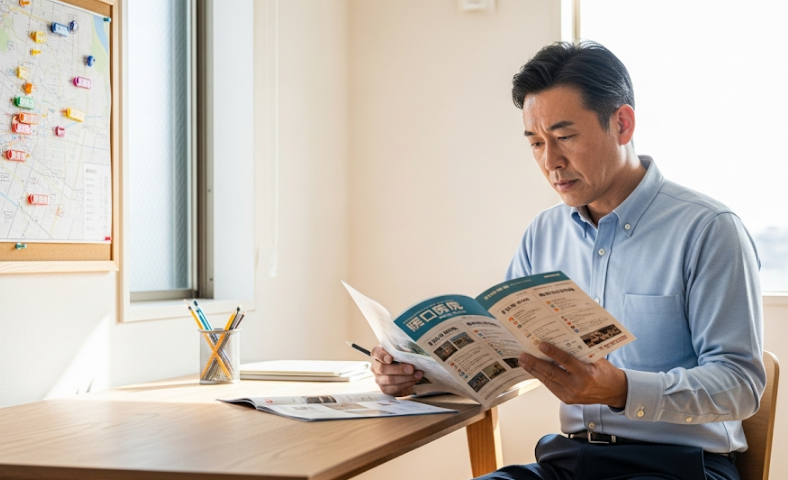
不眠は、それ自体が病気であると同時に、他の様々な病気の「症状の一つ」として現れることがあります。このため、眠れないという訴えの裏に、思わぬ疾患が隠れている可能性を常に念頭に置く必要があります。
例えば、これまでにも触れてきた睡眠時無呼吸症候群は、大きないびきや日中の強い眠気を特徴としますが、夜間に呼吸が止まることで脳が覚醒し、中途覚醒や熟眠障害の原因となります。これを放置すると、高血圧や心臓病、脳卒中のリスクを高めることが知られています。
また、脳神経内科が専門とするレム睡眠行動障害は、夢の内容に合わせて大声で寝言を言ったり、手足を激しく動かしたりする病気で、将来的にパーキンソン病などの神経変性疾患に移行する可能性があるとされています。
さらに、夕方から夜にかけて脚に不快な感覚が現れるむずむず脚症候群は、鉄分不足が原因の一つと考えられており、これも脳神経内科の領域です。
このように、不眠の背景には多様な病気が存在し得ます。自己判断で「ただの不眠症だ」と決めつけず、特にいびきや日中の過度な眠気、異常な寝言や行動など、不眠以外の気になる症状がある場合は、それぞれの専門科で一度詳しい検査を受けることが、将来の大きな病気を防ぐ上で非常に大切になります。

病院での治療に抵抗がある、あるいは薬に頼らず体質から改善したいと考える方にとって、「鍼灸院」での治療は有力な選択肢の一つとなります。
東洋医学において、不眠は「気・血・水」のバランスの乱れや、自律神経の不調和によって引き起こされると考えられています。鍼灸治療は、特定のツボを鍼や灸で刺激することにより、身体全体のバランスを整え、人間が本来持っている自然治癒力を高めることを目的としています。
鍼灸治療のメリットは、薬のような副作用の心配が少なく、身体への負担が穏やかである点です。また、不眠だけでなく、肩こりや冷え、精神的な不安など、本人が抱える他の不調にも同時にアプローチし根本的に心身ともに健康へと導きます。
ただし、鍼灸治療は即効性を期待するものではなく、体質改善を目指してある程度の期間、継続して通うことが基本となります。また、前述の通り、不眠の原因に他の病気が隠れている可能性もあるため、鍼灸治療と並行して、医師の診断も受けておくことが賢明です。もちろんまずは鍼灸院にご相談いただいても医師の診断が必要な際はご紹介いたします。
この記事では、不眠症で何科にいけばいいかという疑問に対して、様々な角度から解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをまとめます。
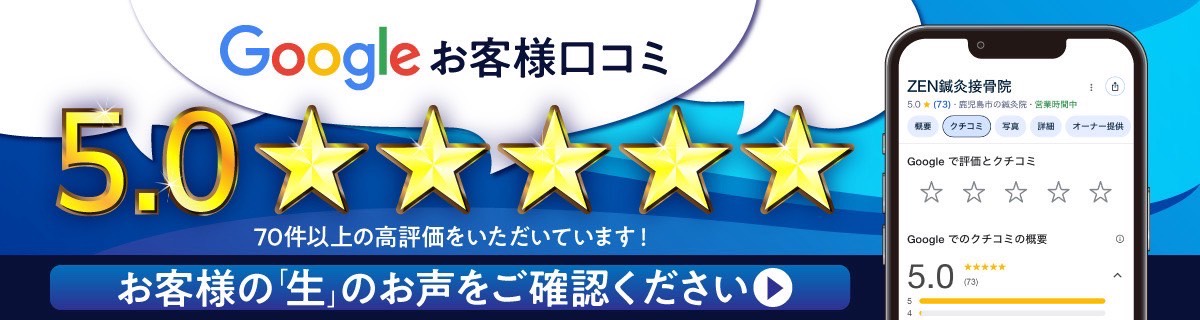


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。