)
こんにちは!鹿児島の不眠専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。日中、耐えがたいほどの眠気に襲われたり、夜しっかり寝たつもりでも朝からひどいだるさを感じたりしていませんか。特に40代からの女性にとって、このような悩みは単なる寝不足ではないかもしれません。実は、更年期にずっと眠いという症状は、多くの方が経験する代表的なサインの一つです。その背景には、女性ホルモンのバランスの変化が深く関わっています。この記事では、なぜ更年期に眠気が強くなるのかという原因を掘り下げ、ご自身でできる対策から、漢方や鍼灸といった専門的なアプローチまで、幅広く解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
更年期とは、閉経を迎える前後の約10年間を指し、日本人女性の平均閉経年齢が約50歳であることから、一般的に45歳から55歳頃がこの期間にあたります。この時期は、女性の心身にとって大きな転換期となり、様々な不調が現れやすくなります。
中でも睡眠に関するトラブルは非常に多く、厚生労働省の調査によれば、更年期にあたる年代の女性の4割から6割が何らかの睡眠問題を抱えていると報告されています。具体的には、「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠った感じがしない」といった不眠の症状です。
このような夜間の睡眠不足が、日中の強い眠気や集中力の低下に直結し、仕事や家事といった日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。特に40代以降の女性は、仕事での責任、子どもの進学や独立、親の介護といった社会的な役割や家庭環境の変化によるストレスも増える時期であり、心身の不調がさらに深刻化しやすいと考えられます。

更年期の様々な不調の根底には、女性ホルモンである「エストロゲン」の分泌量が急激に減少することがあります。卵巣機能の低下に伴い、これまで周期的に分泌されていたエストロゲンが乱高下しながら減少していくため、体の恒常性を保つシステムが混乱してしまうのです。
ただし、日中の「眠気」という症状と、エストロゲンの減少との直接的な因果関係は、現時点では明確に解明されていません。しかし、更年期の女性の多くが経験する「不眠」が、結果として日中の強い眠気を引き起こしていることは広く知られています。
つまり、エストロゲンの減少が直接眠気を引き起こすわけではなく、エストロゲンの減少が引き起こす様々な症状が夜間の睡眠を妨げ、その結果として日中の眠気につながっている、という構図が考えられます。

エストロゲンの分泌量が不安定になると、脳の視床下部にある自律神経のコントロールセンターに影響が及びます。自律神経は、心拍、血圧、体温、呼吸、消化といった生命維持に不可欠な機能を、私たちの意識とは無関係に調整している神経です。
この自律神経が乱れると、本来リラックスすべき夜間にも、体を活動的にさせる交感神経が優位になってしまうことがあります。その結果として現れる代表的な更年期症状が、のぼせやほてり(ホットフラッシュ)、急な発汗、動悸などです。
例えば、就寝中に突然カーッと体が熱くなったり、心臓がドキドキしたりすれば、当然安らかな眠りは妨げられます。これにより、眠りが浅くなる「熟眠障害」や、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」が起こりやすくなるのです。このように睡眠の質が著しく低下するため、日中に強い眠気を感じるようになります。

更年期には、強い眠気とともに「体が鉛のように重い」「何もする気が起きない」といった慢性的なだるさや倦怠感を訴える方も多くいらっしゃいます。このだるさも、エストロゲンの減少と無関係ではありません。
エストロゲンは、エネルギー代謝を調整する役割も担っています。そのため、エストロゲンが減少すると、体内のエネルギー産生効率が低下し、疲れやすさやだるさを感じやすくなるのです。
加えて、前述の通り、自律神経の乱れは全身の血行不良にもつながります。血流が悪くなると、筋肉に疲労物質が溜まりやすくなり、だるさが一層強まるという悪循環に陥ることもあります。睡眠不足による疲労の蓄積と、エネルギー代謝の低下という二つの要因が重なることで、日中の活動意欲が大きく削がれてしまうと考えられます。

更年期に見られる強い眠気や不眠は、単なる更年期症状ではなく、他の病気が隠れている可能性も考慮する必要があります。症状が長期間続く場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合は、自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。特に注意したい代表的な病気には、以下のようなものがあります。
| 病名 | 主な症状と特徴 |
| 閉塞性睡眠時無呼吸症候群 | 睡眠中に喉が塞がり、一時的に呼吸が止まる状態を繰り返す病気です。いびきが特徴で、夜中に何度も目が覚めるため深い睡眠がとれません。女性は閉経後に発症リスクが高まるとされています。 |
| むずむず脚症候群 | 夕方から夜にかけて、特に安静にしている時に、脚に「虫が這うような」「むずむずする」といった不快な感覚が現れる病気です。脚を動かしたくなる強い衝動に駆られ、入眠が困難になります。 |
| 周期性四肢運動障害 | 睡眠中に、本人の意思とは関係なく足首や膝がピクッと動く運動が繰り返し起こる病気です。この動きで脳が覚醒し、眠りが浅くなる原因となります。むずむず脚症候群に合併しやすいと言われています。 |
これらの病気は専門的な診断と治療が必要です。更年期だからと決めつけず、気になる症状があれば専門医に相談しましょう。

日中のつらい眠気は、夜間の睡眠の質を高めることで改善が期待できます。薬に頼る前に、まずは日々の生活習慣を見直すことから始めてみましょう。
毎日できるだけ同じ時間に起床し、同じ時間に就寝することを心がけてください。休日でも、平日との差を1〜2時間以内にとどめるのが理想です。これにより、乱れがちな体内時計が整い、自然な眠気が訪れやすくなります。また、朝起きたらすぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びることも、体内時計をリセットする上で非常に効果的です。
寝室は、眠るためだけの静かで快適な空間にすることが鍵となります。遮光カーテンを利用して光を遮断し、寝具は吸湿性や通気性に優れたものを選びましょう。特にホットフラッシュがある方は、温度調節がしやすいように、薄手の掛け布団やタオルケットを重ねて使うのがおすすめです。寝室の温度や湿度も、ご自身が最もリラックスできる状態に保つ工夫をしてみてください。
就寝の1〜2時間前に、ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、一時的に上がった体温が下がる過程で自然な眠気が促されます。また、日中にウォーキングやヨガなどの適度な運動を取り入れることも、睡眠の質を向上させることが分かっています。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまうため、逆効果になる可能性があるので注意が必要です。

日々の食事内容も、睡眠の質や日中の眠気に影響を与えます。何を、いつ食べるかという点にも少し注意を向けてみましょう。
まず、睡眠を妨げる可能性のあるカフェインやアルコールの摂取は、時間帯を考慮することが大切です。コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインには覚醒作用があるため、少なくとも就寝の4〜5時間前からは摂取を避けるのが賢明です。また、「寝酒」としてアルコールを飲む方もいますが、アルコールは眠りを浅くし、夜中に目が覚める原因となるため、安眠のためには控えるべきです。
一方で、積極的に摂りたい栄養素もあります。例えば、豚肉や大豆製品に豊富なビタミンB群は、エネルギー代謝を助け、疲労回復に役立ちます。また、乳製品や小魚に多く含まれるカルシウムには、神経の興奮を鎮める働きがあると言われています。
特定の食品だけで症状が劇的に改善するわけではありませんが、栄養バランスの取れた食事を一日三食、規則正しく摂ることが、体全体の調子を整え、結果的に睡眠の安定につながります。

生活習慣を改善しても眠気や不眠が続く場合、漢方薬による治療も有効な選択肢の一つです。東洋医学では、心と体のバランスの乱れが不調の原因と考え、個々の体質や症状に合わせて生薬を組み合わせた漢方薬を用いて、体質そのものからの改善を目指します。
更年期の不眠に対しては、特に以下のような漢方薬が用いられることがあります。
| 漢方薬名 | 特徴と向いている方 |
| 加味逍遙散(かみしょうようさん) | 体力が中等度以下で、疲れやすく、精神不安やいらだち、のぼせ、肩こりなどがある方に用いられます。幅広い更年期症状に対応できる代表的な処方です。 |
| 柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう) | 体力が中等度以上で、精神的な不安が強く、動悸や不眠、いらだちなどを伴う方に適しています。神経の高ぶりを鎮める働きが期待できます。 |
漢方薬のメリットは、一つの処方で眠気や不眠だけでなく、だるさ、冷え、イライラといった複数の症状に同時にアプローチできる点です。ただし、効果の現れ方には個人差があり、自分の体質に合わないものを服用しても効果は期待できません。必ず漢方に詳しい医師や薬剤師に相談の上、適切な処方を選んでもらうことが不可欠です。
東洋医学的なアプローチとして、鍼灸治療も更年期のつらい眠気やだるさの緩和に効果が期待できます。鍼灸は、特定のツボ(経穴)に鍼や灸で刺激を与えることで、全身の気血の流れを整え、人間が本来持っている自然治癒力を高める治療法です。
更年期の不調は、自律神経の乱れが大きく関わっていますが、鍼灸にはこの自律神経のバランスを調整する作用があることが分かっています。リラックスを促す副交感神経を優位にすることで、心身の緊張を和らげ、睡眠の質を向上させる効果が期待できるのです。
また、全身の血行を促進する効果も高いため、筋肉の緊張がほぐれ、疲労感が軽減されます。代表的なツボとしては、頭のてっぺんにある「百会(ひゃくえ)」や、手首にある「神門(しんもん)」などがあり、自律神経を整えたり、精神を安定させたりするのに役立ちます。
鍼灸治療は副作用が少なく、体にやさしい治療法ですが、体質改善にはある程度の期間、継続して通うことが一般的です。更年期症状を得意とする信頼できる鍼灸師に相談し、自分に合った施術を受けることをお勧めします。
セルフケアや代替療法を試しても症状が改善しない、あるいは眠気やだるさによって日常生活に深刻な影響が出ている場合は、ためらわずに婦人科を受診しましょう。専門医に相談することで、症状の原因を正しく診断し、適切な治療へと繋げることができます。
婦人科では、問診や血液検査によってホルモンの状態などを確認し、症状の程度に応じて治療法を検討します。代表的な治療法としては、減少したエストロゲンを少量補充する「ホルモン補充療法(HRT)」があります。この治療法は、ホットフラッシュや発汗といった血管運動神経症状に特に高い効果を発揮し、それに伴う不眠の改善も期待できます。
ただし、ホルモン補充療法にはメリットだけでなく、血栓症などのリスクもわずかながら存在するため、誰もが受けられるわけではありません。医師が個々の健康状態を総合的に判断し、治療の利益がリスクを上回る場合に選択されます。
つらい症状を一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも、更年期を健やかに乗り越えるための重要なステップです。
この記事で解説した、更年期のつらい眠気への向き合い方に関する重要なポイントを以下にまとめます。
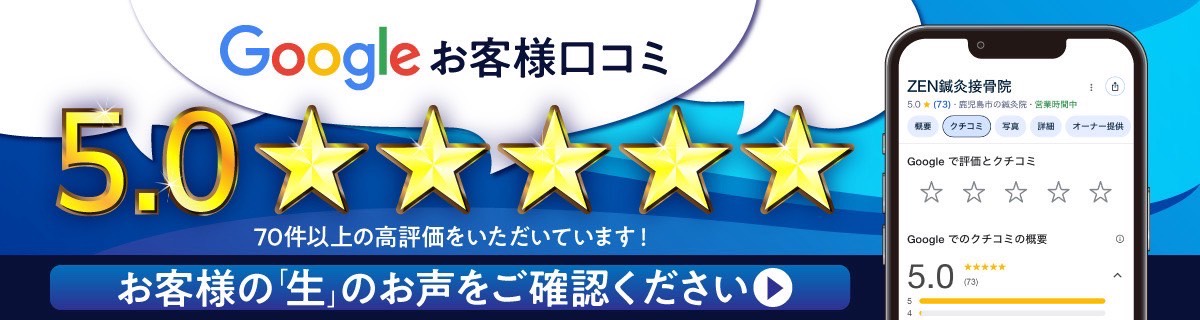


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。