)
こんにちは!鹿児島の自律神経専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。
「腰部脊柱管狭窄症」と診断され、腰やお尻、足にかけての痛みやしびれで、「このまま仕事を続けられるだろうか」「仕事ができない状態になったらどうしよう」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
当院に来られる患者さんからも、特有の症状である間欠性跛行(少し歩くと足が痛くなり、休むとまた歩ける)のせいで通勤や外回りが辛い、というお悩みをよく伺います。
立ち仕事や重量物を扱う仕事はもちろん、実はデスクワークでの同じ姿勢も症状を悪化させることがあり、皆さん本当に悩んでいらっしゃいます。仕事を辞める、あるいは休職すべきか、手術後の復帰はいつからか、経済的な不安から傷病手当金や障害年金について調べる方も多いですね。
この記事では、腰部脊柱管狭窄症と診断された時に、仕事とどう向き合っていくか、どんな対策や制度があるのかについて、私なりの視点でお話ししていこうと思います。

まず、なぜ腰部脊柱管狭窄症になると「仕事ができない」と感じるほど辛くなってしまうのか。それは、この症状特有の「神経の圧迫」が原因ですね。
年齢とともに背骨(腰椎)が変形したり、靭帯が分厚くなったりして、背骨の中にある神経の通り道(脊柱管)が狭くなってしまいます。その結果、中を通っている神経(馬尾や神経根)が圧迫されて、腰や足に様々な症状を引き起こすわけです。
特に仕事に影響するのが、以下の二つの症状かなと思います。
この症状を代表するのが「間欠性跛行」です。私も、患者さんからこの辛さを一番よく伺います。
これは、「少し歩くと足が痛くなったり、しびれたり、重だるくなって歩けなくなる。でも、少し前かがみになって休むと(例えばしゃがみ込む、ベンチに座る)、症状が和らいで、また歩けるようになる」という特徴的な症状ですね。
歩行によって神経への血流が一時的に不足したり、圧迫が強まったりして起こると考えられています。
間欠性跛行による仕事への影響(例)
このように、日常の「歩く」「立つ」という基本動作が制限されるため、仕事の効率が著しく落ちてしまうんです。「周りに迷惑をかけてしまう」と精神的に追い詰められる方も少なくありません。
また、間欠性跛行だけでなく、安静にしていても続く痛みやしびれも問題です。
特に、腰を反らす姿勢(伸展姿勢)で症状が悪化しやすい傾向があります。脊柱管は腰を反らすと狭くなり、逆に丸めると広がる構造になっているからです。
そのため、立っているだけでも(無意識に腰が反り気味になるため)、じわじわと痛みやしびれが強まってくることが多いですね。
こうなると、仕事への集中力も維持しにくくなります。
だから、「もう仕事にならない」と感じてしまう方が多いのも、無理はないかなと思います。
ですが、診断されたからといって、必ずしも「仕事=できない」と決まるわけではありません。大切なのは、ご自身の症状と仕事内容を照らし合わせて、適切な対策を講じることです。

では、具体的にどんな仕事で注意が必要で、どう対策すれば良いのか。ここでは特に相談の多い「デスクワーク」と「立ち仕事」に分けて見ていきましょう。
「狭窄症は歩くと辛いから、座り仕事なら楽」と思われがちですが、実はデスクワークにも大きな落とし穴があります。
それは、「長時間同じ姿勢で座り続けること」です。
座っている姿勢は、立っている時よりも腰椎(腰の背骨)への圧力がかかると言われています。特に、猫背や反り腰といった不適切な姿勢で座り続けると、腰の筋肉が過度に緊張し、血流が悪化します。
血流が悪くなると、神経が回復するために必要な酸素や栄養が届きにくくなり、結果として痛みやしびれを悪化させてしまう可能性があるんです。
デスクワークの対策ポイント

座りっぱなしは腰にとって負担です。こまめに立ち上がるなど、できることから始めていきましょう。
立ち仕事は、腰部脊柱管狭窄症の方にとって、症状が最も出やすいシチュエーションの一つです。先ほどお話ししたように、立っていると腰が反りやすい(伸展しやすい)からです。
「立ちっぱなし」が一番良くないので、いかに負担を減らすかが鍵になります。
レジ、調理場、工場のラインなど、同じ場所で立ち続ける必要がある場合は、意識的な対策が必須です。
立ち仕事の対策ポイント

症状を悪化させないために、以下の動作が多い仕事は、可能であれば配置転換や業務内容の変更を職場に相談することも検討してみてください。
症状悪化につながる動作(具体例)

対策をしても症状が改善せず、通勤もままならない。「もう仕事ができない」と休職や退職が頭をよぎることもあるかと思います。その場合、症状の辛さに加えて、経済的な不安が大きくなりますよね。
そんな時に、生活を支えてくれる公的な制度があります。すぐに「辞める」と決断する前に、こういう制度があることを知っておいてください。
(※重要:私は社会保険労務士ではないため、ここでは一般的な情報提供にとどめます。正確な手続きや条件は、必ず専門家にご確認ください。)
これは、会社員や公務員の方が加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)から支給されるものです。
概要: 腰部脊柱管狭窄症のような「業務外」の病気やケガの療養のために仕事を休み、お給料がもらえない場合に、生活保障として支給されます。
傷病手当金の主なポイント
これは数年前に法改正された重要なポイントです。以前は「支給開始日から1年6ヶ月」だったので、途中で一度復職すると、残りの期間があってももらえなくなる場合がありました。
今は「通算」なので、例えば3ヶ月休んで復職し、また悪化して2ヶ月休む…といった場合でも、トータルで1年6ヶ月分まで支給されるようになりました。これは症状が良くなったり悪くなったりしやすい方にとって、大きな安心材料ですね。(出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金について」)
まずは、お勤め先の総務や人事担当の方、または加入している健康保険組合にご相談いただくのが良いかなと思います。休職中は、経済的な不安が自律神経のバランスを崩す原因にもなりかねませんから、利用できる制度はしっかり活用しましょう。
これは、病気やケガによって日常生活や仕事に著しい制限がある場合に支給される、公的な年金です。
「年金」というと高齢者のイメージかもしれませんが、若い方(現役世代)でも受給できる可能性があります。
ポイント: 腰部脊柱管狭窄症でも、症状の重さ(杖がなければ歩行が困難、介助が常に必要など)が、国が定める障害等級(1級~3級)に該当すれば、受給できる可能性があります。
障害年金の注意点
申請手続きが非常に複雑です。特に「初診日(この症状で初めて医師の診療を受けた日)」を証明することが非常に重要で、この初診日にどの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたかによって、受給できる年金の種類や等級が変わってきます。
申請を考えられる場合は、ご自身で判断せず、年金事務所や、障害年金を専門とする社会保険労務士(社労士)さんにご相談されることを強くお勧めします。
もし、腰部脊柱管狭窄症の発症や悪化が、長年の重量物運搬業務や、極めて不自然な姿勢での作業など、明らかに仕事が原因(業務起因性)であると医学的に認められた場合は、労災保険の対象となる可能性もゼロではありません。
ただし、狭窄症は加齢による変性が主な原因とされることが多いため、業務との因果関係を立証するのは、一般的にかなりハードルが高いと言われています。(「腰痛の労災認定」という基準があります)
こちらも、まずは労働基準監督署や専門家にご相談ください。

保存的な治療(薬やリハビリ、当院のような鍼灸や整体も含む)で改善が見られず、日常生活や仕事に大きな支障が出た場合、手術を選択される方もいらっしゃいますね。
患者さんから「手術したら、いつから仕事に復帰できますか?」と聞かれることも多いですが、これは本当に「術式(手術の方法)」と「仕事内容」によります。
一概には言えませんので、必ず、主治医の先生の判断に(絶対に!)従ってください。
仕事復帰の一般的な目安(※あくまで目安です)
手術には、神経の圧迫を取り除く「除圧術」(内視鏡など)と、背骨の不安定性も伴う場合に骨を固定する「固定術」などがあります。
一番大切なのは、焦って復帰しないことです。
特に「固定術」を受けた場合、骨がくっつく前に無理をすると、固定した金属が緩んだり、別の部分に負担がかかって再発したりするリスクを高めます。
また、手術で神経の圧迫は取れても、安静期間中に筋力が落ちていたり、痛みへの恐怖心が残っていたりすることもあります。医師の指示(コルセットの着用期間など)を守り、適切なリハビリ(ストレッチや筋力強化)を行うことが、結果的に長く仕事を続けるために重要ですね。
腰部脊柱管狭窄症と診断されても、仕事ができないとすぐに諦める必要はありません。まずはご自身の症状と向き合い、職場環境の調整や公的制度の利用、そして適切な治療(保存療法・手術・リハビリなど)を検討し、できることから一つずつ試してみてはいかがでしょうか。
当院でも、鍼灸施術による神経の興奮の鎮静や血流改善、あるいは整体による姿勢バランスの調整など、症状の緩和や日常生活の支障を減らすこと、一日でも長く自分の足で歩けることを目指すお手伝いをしています。辛い時は一人で抱え込まず、ぜひご相談くださいね。
【重要なご注意】
この記事は、一般的な情報提供を目的としています。掲載されている情報はあくまで目安であり、医学的な診断や治療、法律・制度に関する助言に代わるものではありません。
症状の診断、治療(手術の判断を含む)、リハビリテーションについては、必ず医師、医療機関にご相談ください。
公的制度(傷病手当金や障害年金、労災)の申請については、お勤め先の担当部署、健康保険組合、年金事務所、または社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
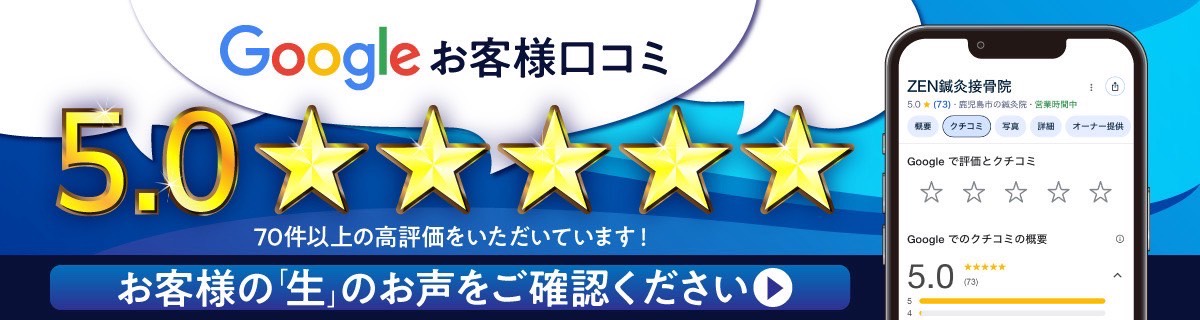


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。