)
こんにちは!鹿児島の不眠専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。「日本人の不眠症の割合は、実際どのくらいなのだろう?」と感じて、検索されたのではないでしょうか。実は、最新の公的なデータによると、成人のかなりの数が睡眠に関する悩みを抱えていることが示されています。
多くの調査で日本人の睡眠不足は指摘されており、患者数の具体的な推移を見ると、その深刻さがうかがえます。一体、日本人の何人に1人が不眠の症状に苦しんでいるのでしょう。世界各国と比較しても、日本の状況は特異であると考えられています。
中には、このつらい状態が一生治らないのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、不眠が治ったきっかけは存在します。この記事では、日本人と不眠症の割合に関する様々な情報を紐解き、その背景にある原因や対策について、専門的なデータを基に分かりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

日本において、不眠は決して珍しい悩みではありません。厚生労働省が実施した令和4年(2022年)の「国民健康・栄養調査」によると、「ここ1ヶ月間、睡眠で休養が十分にとれていない」と回答した人の割合は20.6%にのぼります。これは、日本人の成人の約5人に1人が、睡眠の質に満足していないことを示しています。
また、調査の定義によって数字は変動します。例えば、慢性的な不眠症に限定せず、「寝つきが悪い」「夜中に目が覚める」といった不眠症状を一時的にでも経験したことがある人は、成人の3割から5割に達するという報告もあります。
このように言うと、非常に多くの人が睡眠に関する何らかの課題を抱えている実態が浮かび上がります。ただし、これらの数字は調査の定義や対象者によって異なるため、複数のデータを比較検討することが大切です。

不眠の悩みは、全ての人に等しく現れるわけではありません。年齢や性別によって、その割合には明確な違いが見られます。
一般的に、不眠症は20代から30代で始まり、加齢と共に増加する傾向があります。特に高齢者では、睡眠が浅くなる、途中で目が覚めやすくなるといった生理的な変化もあり、有病率が高くなることが知られています。
また、性別で比較すると、不眠の悩みを抱えるのは男性よりも女性に多い傾向があります。ある調査では、日本人の不眠の有病率は男性が約12.2%、女性が14.6%と報告されており、女性の方がやや高い数値を示しています。
| 対象 | 特徴 |
| 年齢 | 20~30代で始まり、加齢とともに有病率が増加する傾向 |
| 性別 | 男性よりも女性の方が不眠の悩みを抱える割合が高い |
| 働き世代 | 男性の30~50代、女性の40~60代では睡眠時間が6時間未満の人が4割を超える |
これらのデータから、特定の年代や性別で睡眠の問題がより顕著になることが分かります。そのため、自身の状況と照らし合わせながら対策を考えることが鍵となります。
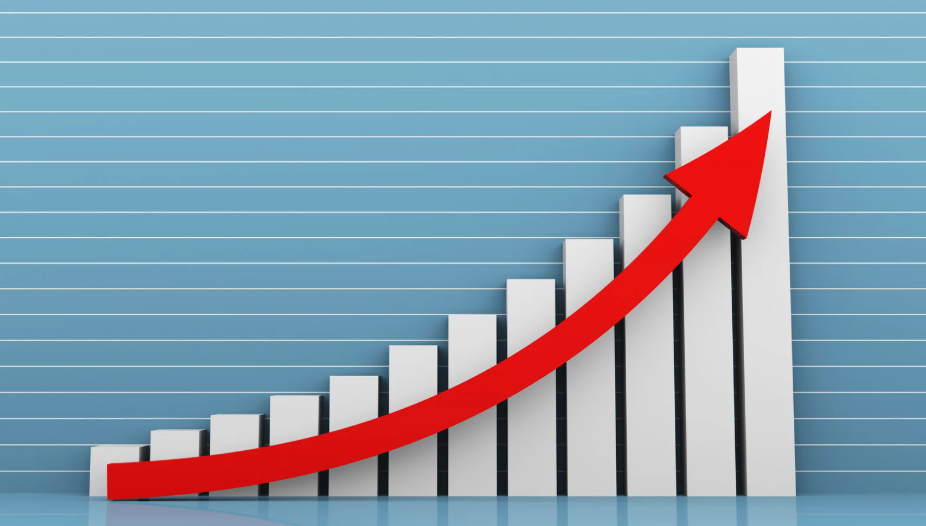
不眠の問題は、近年さらに深刻化している可能性があります。前述の通り、令和4年(2022年)の「国民健康・栄養調査」では、睡眠で十分な休養がとれていない人の割合は20.6%でした。
注目すべきは、この数値が過去の調査結果と比較して増加傾向にある点です。平成21年(2009年)の調査から見ると、この割合は統計的にも有意に増加していると報告されています。
この背景には、現代社会におけるストレスの増大、ライフスタイルの多様化、デジタルデバイスの普及による生活リズムの乱れなど、様々な要因が関係していると考えられます。社会環境の変化が、日本人の睡眠の質に直接的な影響を及ぼしていると言えるかもしれません。このため、個人の努力だけでなく、社会全体で睡眠の重要性への認識を高めていく必要があります。

日本人の睡眠問題は、国内だけの話ではありません。国際的に見ても、日本の状況は際立っています。
経済協力開発機構(OECD)が2021年に公表した調査によると、加盟33カ国中、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で最下位でした。調査対象国の平均が8時間28分であることから、日本人は世界的に見ても突出して睡眠時間が短い国民であることが分かります。
この睡眠時間の短さは、経済的な損失にもつながっています。米国のシンクタンク「ランド研究所」の試算によれば、日本の睡眠不足による経済損失は年間約20兆円にのぼり、これはGDP比で2.92%に相当します。このGDP比での損失は、アメリカやイギリス、ドイツなどの先進国と比較しても最も大きい数値です。
これらのことから、日本人の睡眠不足は個人の健康問題に留まらず、国家的な経済課題でもあることが明確になります。

「ただの寝不足」と軽視されがちな不眠ですが、慢性化すると心身に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。十分な睡眠がとれない状態が続くと、生活の質が低下するだけでなく、重大な病気のリスクを高めることが多くの研究で指摘されています。
具体的には、高血圧、糖尿病、心疾患、肥満といった生活習慣病のリスクが上昇します。睡眠中は体の修復やホルモンバランスの調整が行われますが、この機能が十分に働かないためです。
さらに、精神面への影響も無視できません。不眠はうつ病の主要なリスク因子の一つであり、自殺のリスクを高めることも報告されています。また、近年の研究では、高齢者の睡眠不足がアルツハイマー型認知症の原因物質とされるアミロイドβの脳内蓄積を促進し、認知機能の低下に関連することも示唆されています。日中の眠気による集中力低下や事故のリスクも含め、睡眠不足は多岐にわたる深刻な問題を引き起こすのです。

不眠症と一言で言っても、その症状の現れ方は人それぞれです。主に4つのタイプに分類され、これらが単独で、あるいは複数組み合わさって現れることがあります。自分の不眠がどのタイプに当てはまるかを知ることは、適切な対策を考える上で最初のステップとなります。
| タイプ | 主な症状 |
| 入眠困難 | 床に就いても、30分~1時間以上なかなか寝付けない。 |
| 中途覚醒 | いったん眠っても、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後再び眠るのが難しい。 |
| 早朝覚醒 | 起きたい時刻よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、それから眠れない。 |
| 熟眠障害 | 睡眠時間は足りているはずなのに、眠りが浅く、ぐっすり眠れたという満足感が得られない。 |
これらの夜間の症状に加え、その結果として生じる日中の不調(眠気、倦怠感、集中力低下など)も不眠症の重要な症状の一部です。例えば、入眠困難に悩んでいる人は、夜に「また眠れないかもしれない」という不安を抱えがちです。一方で、中途覚醒や早朝覚醒は、特に加齢と共に増える傾向が見られます。

つらい不眠が続くと、「この状態が一生続くのではないか」と大きな不安を感じる方も少なくありません。確かに、不眠症は慢性化しやすいという特徴があり、数ヶ月から数年にわたって症状が続くケースも見られます。
しかし、不眠症が必ずしも「一生治らない病気」というわけではありません。適切な治療や生活習慣の見直しによって、症状が大きく改善する人はたくさんいます。重要なのは、不眠の原因を正しく理解し、自分に合った対策を根気強く続けることです。
注意点として、不眠を放置すると症状が固定化しやすくなる可能性があります。また、自己判断で睡眠薬代わりにお酒を飲むといった誤った対処法は、かえって睡眠の質を下げ、問題を悪化させることがあります。不安を抱え込まず、早い段階で専門家に相談することが、回復への近道となります。

不眠の改善には、専門的な治療だけでなく、日々の生活習慣を見直すことが非常に効果的です。ここでは、不眠が治ったきっかけにもなり得る生活習慣のポイントを、「控えるべきこと」と「取り入れたいこと」に分けて紹介します。
睡眠の質を低下させる可能性があるため、以下の習慣は特に就寝前に避けることが推奨されます。
一方で、良質な睡眠を促すためには、以下の習慣を日常生活に取り入れることが大切です。

生活習慣の改善を試みても不眠が続く場合は、医療機関での治療が選択肢となります。治療は、薬物治療と非薬物治療に大別されます。
薬物治療では、主に睡眠薬が用いられます。近年では、脳を覚醒させる物質の働きを抑える「オレキシン受容体拮抗薬」や、自然な眠りを誘うホルモンに作用する「メラトニン受容体作動薬」など、依存性のリスクが比較的低い新しいタイプの薬も登場しています。
一方、薬に頼らない治療法として、「認知行動療法(CBT-I)」があります。これは、睡眠に関する誤った思い込みや習慣を修正し、眠りやすい心身の状態を作ることを目指す心理療法です。
鍼灸もWHO(世界保健機関)が不眠症の適応疾患として認めています。
どこに相談すればよいか分からない場合、まずはお近くのかかりつけ医に相談してみるのがよいでしょう。より専門的な治療が必要な場合は、精神科や心療内科を紹介してもらえます。最近では、診療科名に「睡眠障害」を掲げられるようにする動きもあり、今後は専門の医療機関がより見つけやすくなることが期待されます。

不眠症のメカニズム解明や治療法の開発は、現在も進歩し続けています。今後の研究によって、より効果的で副作用の少ない治療が可能になることが期待されています。
例えば、近年の脳画像研究では、不眠症が脳内の特定の神経回路網(デフォルトモード・ネットワーク)の異常と関連している可能性が示唆されています。このような脳科学的なアプローチは、不眠症の根本的な原因解明につながるかもしれません。
また、テクノロジーの活用も進んでいます。脳波などを測定して睡眠の状態を詳細に分析する「スリープテック」と呼ばれるサービスが登場し、個人の睡眠データを基にした改善アドバイスを提供する企業も増えています。これらの技術がさらに発展・普及すれば、一人ひとりの状態に合わせた、よりパーソナライズされた睡眠ケアが実現するでしょう。
この記事で解説した、日本人の不眠症に関する重要なポイントを以下にまとめます。
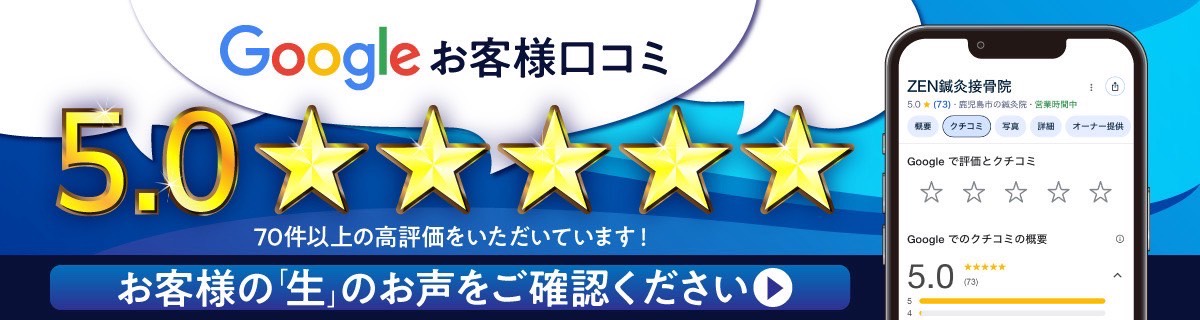


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。