)
こんにちは!鹿児島の不眠専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。夜眠れない苦しさに加え、なぜか昼眠いというつらい症状に悩んでいませんか。仕事や家事に集中できず、時には耐えられないほどの眠気に襲われることもあるでしょう。その不調の裏には、単なる寝不足だけでなく、日々の大きなストレスや、場合によってはうつなどの心の状態が関係しているかもしれません。このつらい悪循環から抜け出すためには、まずその原因を正しく理解し、適切な対処法を知ることが大切です。
この記事では、不眠症で日中眠い状態になってしまう根本的な原因を多角的に解説し、ご自身で今すぐ試せる具体的な対処法から、体質改善を目指す東洋医学のアプローチまで、幅広くご紹介します。

夜間に十分な睡眠がとれないにもかかわらず、日中に強い眠気を感じるのは、心身が発している危険信号です。この状態は、睡眠の質が著しく低下し、体の自然なリズムが崩れてしまっている「負のサイクル」に陥っていることを示しています。
私たちの体には、約24時間周期で心身の状態を調整する「体内時計」が備わっています。しかし、夜間にぐっすり眠れない状態が続くと、この体内時計が乱れ始めます。その結果、夜になるべき時間に体や脳が休息モードに切り替わらず、逆に日中の活動すべき時間帯に強い眠気として現れるのです。
さらに、この日中の眠気を解消しようとして午後に長い昼寝をとってしまうと、夜の寝つきがさらに悪化します。これが「夜眠れない→日中眠い→昼寝をする→さらに夜眠れなくなる」という悪循環を生み出す典型的なパターンです。このサイクルを断ち切るためには、まずなぜ夜眠れないのか、その根本的な原因に目を向けることが不可欠となります。
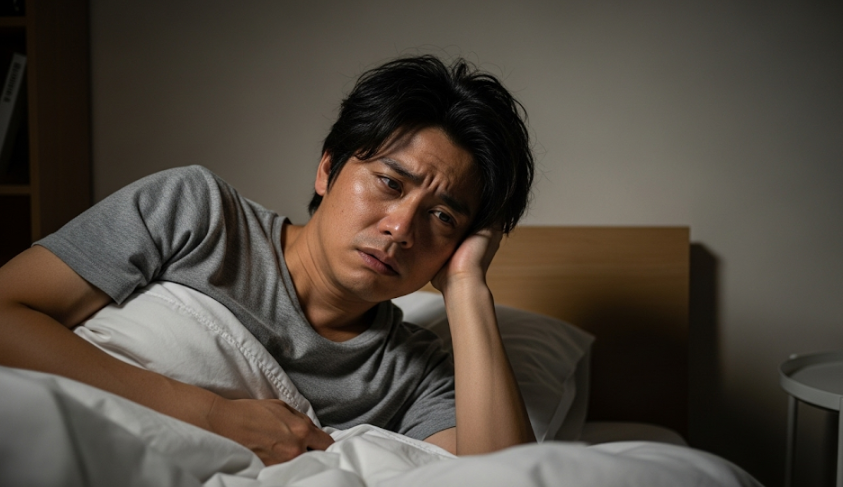
不眠症の原因は一つに特定できるものではなく、多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合って生じます。これらの原因を正しく理解することが、改善への第一歩となります。原因は大きく分けて、以下の3つに分類されると考えられます。
私たちの日常生活の中には、睡眠を妨げる習慣が数多く潜んでいます。例えば、就寝前のカフェインやアルコールの摂取は、脳を覚醒させたり、睡眠の質を浅くしたりする代表的な要因です。また、スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、寝つきを悪くさせます。不規則な食事時間や夜遅くの運動も、体内時計を乱す原因となり得ます。
何らかの体の病気や不調が、睡眠を妨げているケースも少なくありません。関節リウマチなどの痛みを伴う疾患、アトピー性皮膚炎などのかゆみ、頻尿や咳といった症状は、夜間の覚醒を引き起こします。特に注意が必要なのが「睡眠時無呼吸症候群」です。これは睡眠中に何度も呼吸が止まる病気で、深い睡眠を妨げ、日中の激しい眠気の直接的な原因となります。
前述の通り、精神的なストレスは不眠の最大の原因の一つです。仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、将来への不安などが頭から離れず、心身が緊張状態のままでは安らかな眠りは得られません。また、うつ病や不安症といった精神疾患は、不眠を主症状として伴うことが非常に多いことが知られています。これらの要因がどのように影響しているか、ご自身の生活を振り返ってみることが大切です。

精神的なストレスは、不眠を引き起こす非常に強力な要因です。私たちの体は、ストレスを感じると、危機に対応するために交感神経を活発化させ、心身を「闘争か逃走か」のモードに切り替えます。このとき、副腎からコルチゾールというストレスホルモンが分泌されます。コルチゾールには血糖値を上げ、体を覚醒させる働きがあるため、日中の活動には不可欠です。
しかし、本来であれば夜間に分泌量が減少するはずのコルチゾールが、強いストレスによって高いまま維持されると、脳が興奮状態から抜け出せなくなります。その結果、ベッドに入っても仕事の失敗や人間関係のトラブルなどが頭を駆け巡り、リラックスすることができず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅く何度も目が覚めたりするのです。
さらに問題なのは、眠れないこと自体が新たなストレスを生み出してしまう点です。「今日もまた眠れないのではないか」という予期不安が交感神経をさらに刺激し、不眠を悪化させるという悪循環に陥りやすくなります。このように、ストレスと不眠は密接に結びついており、睡眠の問題を解決するためには、ストレスをいかに上手に管理し、心身をリラックスさせるかが鍵となります。

「ただの不眠」だと軽視していた症状が、実はうつ病や不安症といった精神疾患のサインである可能性は十分に考えられます。不眠は、これらの疾患において最も一般的にみられる症状の一つであり、特にうつ病患者の約8割が睡眠に関する何らかの問題を抱えていると言われています。
うつ病に伴う不眠には、寝つきが悪い「入眠障害」、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」、そして予定よりずっと早く目が覚めてしまい二度寝できない「早朝覚醒」といった特徴があります。これらの症状によって睡眠の質が著しく低下するため、日中には強い眠気や、何をしても晴れない倦怠感、集中力の低下などが現れます。
もし、不眠や日中の眠気に加えて、「これまで楽しめていたことに興味が持てなくなった」「気分が一日中落ち込んでいる」「食欲がない、または過食してしまう」といった状態が2週間以上続いている場合は、注意が必要です。これらの心の不調は、意志の力だけで解決するのは困難です。自己判断で抱え込まず、心療内科や精神科といった専門の医療機関に相談することが、早期回復への最も確実な道筋となります。

日中の眠気が、単なる「眠い」というレベルを超え、自分の意思ではどうにもならないほど強烈な場合、それは不眠症から派生した症状ではなく、別の睡眠障害が原因かもしれません。特に注意すべき病気として「過眠症」と「睡眠時無呼吸症候群」が挙げられます。
過眠症の代表例である「ナルコレプシー」は、場所や状況を選ばずに突然、抗いがたい眠気に襲われて眠り込んでしまう「睡眠発作」を主症状とします。重要な会議中や車の運転中など、通常ではありえない場面で眠ってしまうため、日常生活に大きな支障をきたします。
一方、「睡眠時無呼吸症候群」は、睡眠中に気道が塞がることで呼吸が繰り返し止まり、体が低酸素状態に陥る病気です。本人は無自覚なことが多いのですが、脳は呼吸を再開させるために何度も覚醒を繰り返しており、結果として睡眠が細切れになります。このため、夜間に十分な時間寝ているつもりでも、深刻な睡眠不足状態となり、日中に激しい眠気や集中力の低下を引き起こすのです。
これらの病気は、放置すると重大な事故につながる危険性や、生活習慣病のリスクを高めることが知られています。いびきがひどい、眠っているときに呼吸が止まっていると指摘されたことがある、といった心当たりのある方は、睡眠障害を専門とする医療機関を受診することを強く推奨します。

不眠症と日中の眠気を改善するためには、専門的な治療の前に、まずご自身の生活習慣を見直すことが基本となります。私たちの体は非常に繊細なリズムを持っており、それを整えることで睡眠の質は大きく向上する可能性があります。
最も大切なのは、毎日同じ時間に起床し、朝日を浴びることです。光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気を促すホルモン「メラトニン」の分泌リズムが整います。休日でも平日と同じ時間に起きるのが理想です。
食事は決まった時間に摂るように心がけましょう。特に朝食は、体内時計を正常に働かせるための重要なスイッチとなります。また、夕食は就寝の3時間前までに済ませ、消化の良いものを適量とるのが望ましいです。
カフェインを含むコーヒーや紅茶、緑茶などは、覚醒作用が4時間以上続くことがあるため、午後以降の摂取は避けるのが賢明です。また、アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、睡眠の後半部分を浅くし、夜中に目が覚める原因となるため、寝酒は逆効果です。喫煙も同様に覚醒作用があるため控えましょう。
これらの基本的な対策は、すぐに劇的な効果が現れるわけではありませんが、継続することで着実に体質改善につながります。焦らず、できることから一つずつ取り組んでみてください。

前述の通り、基本的な生活習慣の見直しに加え、就寝前に心と体をリラックスさせる「入眠儀式」を取り入れることで、睡眠の質はさらに高まります。ここでは、今日からでも始められるセルフケアのコツをいくつかご紹介します。
スマートフォンやパソコン、テレビなどが発するブルーライトは、脳を覚醒させてしまいます。少なくとも就寝1時間前にはこれらの電子機器の使用をやめ、部屋の照明を暖色系の間接照明などに切り替えて、穏やかな光の中で過ごすようにしましょう。
就寝の90分から120分前に、38~40℃程度のぬるめのお湯に20~30分ほどゆっくり浸かるのが効果的です。入浴によって一時的に上がった深部体温が、ベッドに入る頃に自然と下がり始め、これが強い眠気を誘います。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため避けましょう。
穏やかな音楽を聴く、アロマオイルの香りを楽しむ、カフェインの入っていないハーブティーを飲むなど、自分が心からリラックスできると感じる方法を見つけましょう。また、軽いストレッチで体の緊張をほぐすのも良い方法です。これらの習慣は、脳に「これから眠る時間だ」という合図を送る役割も果たします。

西洋医学が不眠を一つの症状として捉えるのに対し、東洋医学では、その人の体質や不眠の現れ方から原因を探り、いくつかのタイプに分類してアプローチします。これは、体全体のバランスの乱れが不眠を引き起こすという考え方に基づいています。ここでは代表的なタイプをいくつかご紹介します。
| タイプ | 主な症状や特徴 | 東洋医学的な原因の考え方 |
| 肝鬱化火(かんうつかか) | イライラして寝つけない、怒りっぽい、夢を多く見る | 過度なストレスにより「肝」の気の巡りが滞り、熱を帯びて精神をかき乱している状態 |
| 心脾両虚(しんぴりょうきょ) | くよくよ考え事をして眠れない、眠りが浅い、食欲不振、疲れやすい | 思い悩みや過労により、精神を司る「心」と消化器系の「脾」の働きが共に弱っている状態 |
| 心腎不交(しんじんふこう) | 寝つけない、動悸、ほてり、めまい、足腰のだるさ | 加齢や過労で体を潤す「腎」の力が弱まり、体の熱を司る「心」の熱を冷ませなくなった状態 |
| 痰熱内擾(たんねつないじょう) | 胸苦しさや不快感で眠れない、寝起きが悪い、めまい、吐き気 | 暴飲暴食などにより、体内に不要な水分(痰)と熱がこもり、精神を不安定にさせている状態 |
このように、東洋医学では「なぜ眠れないのか」を多角的に分析します。自分の不眠がどのタイプに近いかを知ることは、鍼灸などの治療を受ける上で、また日々の養生法を見つける上で大きなヒントとなります。

薬に頼らずに不眠を改善したい、体質から根本的に見直したいと考える方にとって、鍼灸は有効な選択肢の一つです。鍼灸治療の大きな目的は、乱れてしまった自律神経のバランスを整えることにあります。
私たちの体は、活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」がシーソーのようにバランスを取りながら機能しています。しかし、ストレスや不規則な生活が続くと、交感神経が過剰に働き続け、夜になっても心身が興奮状態から抜け出せなくなってしまいます。これが不眠の大きな原因です。
鍼灸施術では、手足や背中などにある特定のツボに、髪の毛ほどの細い鍼でごく浅い刺激を与えたり、温かいお灸を据えたりします。この心地よい刺激が、過敏になっている交感神経の働きを鎮め、心身をリラックスさせる副交感神経を優位に切り替える手助けをします。
もちろん、効果には個人差があり、一度の施術で劇的に改善するわけではありません。しかし、治療を継続することで、体が本来持っている「眠る力」を徐々に取り戻していくことが期待できます。特に、薬の副作用が心配な方や、様々なセルフケアを試しても改善が見られなかった方には、一度試してみる価値があるアプローチと言えるでしょう。

鍼灸治療を継続することで、単に「眠れるようになる」だけでなく、心身に様々な良い変化が期待できます。夜間の睡眠の質が向上することは、日中の活動の質を大きく左右するからです。
まず最も期待されるのは、睡眠そのものの改善です。具体的には、「ベッドに入ってから寝つくまでの時間が短くなる(入眠障害の改善)」、「夜中に目が覚める回数が減り、朝までぐっすり眠れるようになる(中途覚醒の改善)」、「予定より早く目が覚めてしまうことがなくなる(早朝覚醒の改善)」といった効果が挙げられます。これにより、睡眠時間だけでなく、睡眠の「質」が向上し、朝の目覚めがすっきりとしたものに変わっていきます。
夜間に質の良い睡眠がとれるようになると、日中のつらい症状も自然と和らいでいきます。「耐えがたいほどの眠気が軽減する」、「仕事や勉強への集中力が高まる」、「理由のない倦怠感や疲労感がなくなる」といった変化を感じられるでしょう。また、自律神経のバランスが整うことで、精神的にも安定し、「イライラしにくくなった」、「気分の落ち込みが減った」といった副次的な効果も多く報告されています。
このように、鍼灸は不眠という一点の問題を解決するだけでなく、生活全体の質(QOL)を高めることにも貢献する可能性があります。
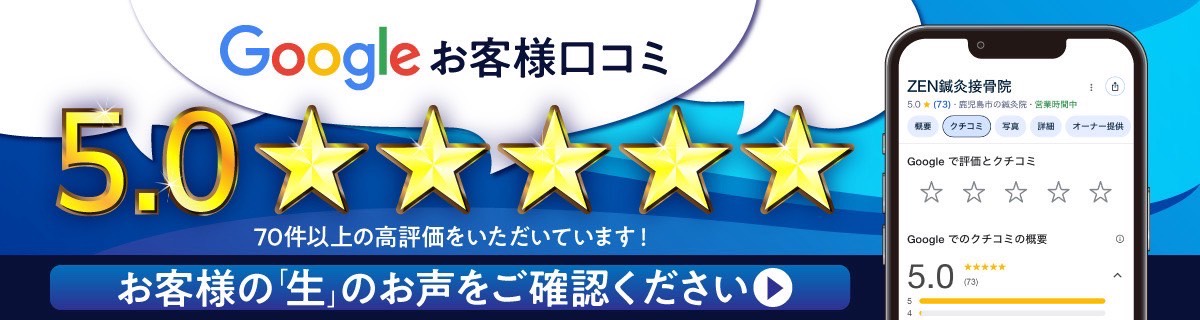


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。