)
こんにちは!鹿児島の自律神経専門 ZEN鍼灸接骨院の栫漸(かこいぜん)です。「胸の脇やお腹の上あたりが張って苦しい…」そんな不快感の正体は、もしかすると東洋医学でいう「胸脇苦満(きょうきょうくまん)」かもしれません。胸脇苦満とは一体どのような状態を指すのでしょうか。
この記事では、胸脇苦満の具体的な症状や、その主な原因として考えられるストレスとの関係について詳しく解説します。また、息苦しい感覚や背中の痛みといった関連する不調にも触れながら、自宅で試せる簡単なストレッチやツボ押しなどのセルフケア方法、専門家によるアプローチまで、幅広くご紹介します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

胸脇苦満とは、主に両側の肋骨の下から脇腹(この領域を漢方では「季肋部(きろくぶ)」と呼びます)にかけて、張った感じや圧迫感を覚える状態を指す、漢方医学の所見(診察上のサイン)です。
これは特定の病名を指すものではなく、体に何らかの不調があることを示すサインとして捉えられています。
診察の際には、医師が患者の肋骨の下あたりに指を滑り込ませるようにして押します。その時に、患者が圧痛(押されたときの痛み)や、指が入りにくいほどの強い抵抗感、または息苦しさのような不快感を覚えるかどうかで判断されます。
人によっては「みぞおちから脇腹が苦しい」と感じたり、単なる膨満感として自覚されたりすることもありますが、漢方医学的な診察(腹診)では、他者が押した際の明確な「抵抗」や「圧痛」の有無が重視されます。

胸脇苦満が起こる原因は一つではなく、身体的な炎症から精神的な要因まで多岐にわたると考えられています。
東洋医学では、特に横隔膜周囲の緊張や、エネルギー(気)の流れの滞りが深く関わっているとされます。
データベースの情報によれば、気管支炎、肺炎、胸膜炎、肝炎といった呼吸器や上部消化器など、横隔膜の周辺にある臓器に炎症がある場合、胸脇苦満の所見が現れやすいとされています。
横隔膜は、胸とお腹を隔てるドーム状の筋肉で、呼吸において中心的な役割を果たします。しかし、私たちが不安や緊張を感じていると、無意識のうちに息を詰めたり、呼吸が浅くなったりしてしまいます。このような状態が続くと、横隔膜そのものが硬く緊張し、こわばってしまいます。この横隔膜の持続的な緊張が、肋骨下部の圧迫感や抵抗感として感じられると考えられています。
東洋医学では、精神的なストレスが続くと「肝(かん)」の機能が乱れると考えます。肝は、全身のエネルギー(気)の流れをスムーズに調整する役割(疏泄作用)を持つとされます。ストレスによってこの機能が低下すると、気の巡りが滞る「肝気鬱結(かんきうっけつ)」と呼ばれる状態になります。この気の滞りが、特に肝の経絡(エネルギーの通り道)が通る胸や脇腹の張り・苦しさとして現れるのが胸脇苦満です。
胸脇苦満は、多くの情報源で指摘されている通り、現代社会において特に「ストレス」と非常に深い関係がある所見とされています。
その理由は、継続的な精神的ストレスが自律神経のバランスを崩し、体を常に緊張状態(交感神経が優位な状態)にしてしまうためです。
人が強いストレスを感じると、筋肉は無意識にこわばります。ある説では、これはかつて動物が捕食者に襲われた際に、急所である首やお腹の筋肉を硬くして身を守ろうとした防御反応の名残とも考えられています。
現代社会では捕食者に襲われることはありませんが、仕事上のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安などが持続的なストレス源となります。体がこれらのストレスに反応し、筋肉、特に呼吸に関わる横隔膜や腹壁を緊張させたままの状態が続きます。この緊張が固定化し、慢性的な張りや圧痛として現れるのが、ストレス性の胸脇苦満の一因とみられています。

胸脇苦満と同時に「息苦しい」「息を吸っても酸素が薄く感じる」「呼吸が浅い」といった症状を訴える場合、その背景には呼吸の仕方が関係している可能性があります。
前述の通り、ストレスなどによって横隔膜が硬く緊張すると、本来リラックスした深い呼吸(腹式呼吸)で使われるはずの横隔膜がうまく機能しなくなります。
私たちの呼吸には、主に横隔膜を上下させて行う「腹式呼吸」と、肋骨の間にある肋間筋(スペアリブの部分の筋肉)を使って行う「胸式呼吸」があります。
横隔膜が緊張して硬くなると、深くゆったりとした腹式呼吸がしにくくなり、無意識のうちに浅い胸式呼吸が中心となります。胸式呼吸では、肺を大きく広げる能力に限界があります。そのため、息苦しさを感じると、体はそれを補おうとして、首や肩の筋肉まで動員して無理に胸郭を広げようとします。
この結果、「吸っても吸っても酸素が入ってこない」ような息苦しさや、胸の痛み、動悸、さらにはパニックのような症状を引き起こしやすくなると考えられています。
あまり知られていませんが、お腹側(体の前面)の所見である胸脇苦満は、実は背中側にある「棘下筋(きょくかきん)」という筋肉の状態と密接に関連していると言われています。
ある専門家の経験則では、胸脇苦満が認められる人のほぼ100%に、この棘下筋にも圧痛(押したときの痛み)やしこり(スジ状の硬さ)が見つかるとされています。
棘下筋は、肩甲骨の表面に張り付いている筋肉の一つで、肩関節を安定させる役割(インナーマッスル)を持ちます。ストレスなどで体が緊張すると、肩周りがこわばり、この棘下筋も硬くなりやすいのです。
興味深いことに、胸脇苦満の原因の一つとされる横隔膜を動かす神経(横隔神経)と、棘下筋を動かす神経(肩甲上神経)は、どちらも頸髄(首の神経)の同じ高さ(主に第5頸神経)から出ているとされています。このため、両者は神経レベルで密接に連携しており、お腹側の横隔膜の緊張が、背中側の棘下筋の緊張や圧痛として反映されると考えられています。
実際、胸脇苦満の所見がなくても、ストレスが多い人には棘下筋の圧痛が見られることも多く、棘下筋の圧痛は胸脇苦満よりも感度が高いストレスサインである可能性も指摘されています。
漢方治療において、胸脇苦満は「柴胡(さいこ)」というセリ科の植物の根を主薬とする「柴胡剤(さいこざい)」を選ぶための非常に重要な目標(サイン)とされています。
柴胡には、東洋医学でいう「肝」の機能(気の流れや自律神経の調整)を整え、体にこもった熱や炎症を和らげる働きがあるとされるためです。柴胡剤は、風邪薬から胃薬、精神安定薬の代わりまで幅広く応用され、特にストレスによる心身の緊張を解きほぐす目的で現代でも広く用いられます。
ただし、柴胡剤には多くの種類があり、胸脇苦満の抵抗感の強さや、その人の体力(実証・虚証)、便秘の有無、その他の症状(イライラ、不安、冷えなど)によって厳密に使い分けられます。
| 漢方薬名 | 対象となる体力(目安) | 抵抗・圧痛の強さ | 主な関連症状の例 |
|---|---|---|---|
| 大柴胡湯(だいさいことう) | 体力充実(実証) | 強い | 肥満気味、便秘、肩こり、高血圧 |
| 小柴胡湯(しょうさいことう) | 体力中等度 | 中程度 | 食欲不振、吐き気、風邪が長引く |
| 柴胡桂枝湯(さいこけいしとう) | 体力中等度~やや虚弱 | 中程度 | 腹痛、微熱、頭痛、風邪の中期~後期 |
| 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう) | 体力中等度以上 | 中~強 | 精神不安、動悸、不眠、イライラ |
| 柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう) | 体力虚弱(虚証) | 弱い | 冷え性、貧血、動悸、息切れ、不眠 |
注意点として、柴胡剤は効果が期待できる反面、体質(証)に合わないと効果が出ないばかりか、かえって体調を崩す可能性もあります。例えば、小柴胡湯は過去に間質性肺炎などの副作用が大きく報道された経緯もあり、安易な自己判断は避けるべきです。
胸脇苦満を感じ、漢方薬を試したい場合は、必ず医師や薬剤師、漢方の専門家に相談し、ご自身の体質に合った処方を選んでもらうことが大切です。

胸脇苦満の原因の一つである横隔膜や肋骨周りの筋肉の緊張を和らげるためには、セルフケアとしてストレッチが有効です。
特に、浅くなった呼吸を深くするために「腹式呼吸」を意識し、硬くなった横隔膜を直接動かしてストレッチすることが役立ちます。
まずは自分の普段の呼吸が胸式になっていないか確認してみましょう。全身が映る鏡の前に立ち、大きく深呼吸をしてみてください。もし両肩が持ち上がってしまうようであれば、胸式呼吸が優位になっています。
リラックスした姿勢(座っても寝ていても構いません)で、両手を肋骨の下あたりに置きます。 まず、口からゆっくりと時間をかけて息を吐き出し、お腹をへこませます。 吐き切ったら、今度は鼻からゆっくり息を吸い込みながらお腹を膨らませます。 この時、手で触れている横隔膜が上下にダイナミックに動くのを意識するのがポイントです。
座った状態または立った状態で、片方の手(例えば右手)を頭の後ろに当てます。 息をゆっくり口から吐きながら、体を真横(左側)に倒します。この時、頭に当てた右肘を天井に引き上げるように意識すると、右の脇腹(胸郭の横側)が心地よく伸びるのを感じられます。 息を吸いながらゆっくりと元の姿勢に戻ります。 反対側も同様に、無理のない範囲で3回ほど繰り返します。
これらのストレッチは、痛みを感じない、リラックスできる範囲で行うことが大切です。
東洋医学では、胸脇苦満に関連する「肝」の機能を整えたり、滞った「気」の巡りを良くしたりするツボが知られています。
これらのツボを刺激することで、セルフケアとして心身の緊張緩和を助けることが期待できます。

足の甲にあり、足の親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみに位置します。「肝」の経絡に属する重要なツボで、ストレスやイライラを和らげ、気の巡りを整えるツボとして有名です。

膝の外側、斜め下にある骨の出っ張り(腓骨頭=ひこっとう)を探し、そのすぐ手前下のくぼみにあります。「胆」の経絡に属し、筋肉の緊張やこわばりを緩めるのに役立つとされます。胸脇苦満の所見がある場合、このツボ(特に右側)に圧痛が出やすいとも言われています。
ツボ押しは、「痛気持ちいい」と感じる程度の強さで、息を吐きながらゆっくりと数秒間押し、息を吸いながら緩める、という動作を数回繰り返します。強く押しすぎると筋肉を痛めることもあるため、無理のない範囲で行ってください。
漢方薬やセルフケア(ストレッチ、ツボ押し)を試しても改善が見られない場合や、痛み・苦しさが強い場合は、鍼灸院などの専門家に相談するのも一つの有効な選択肢です。
鍼灸治療では、胸脇苦満というお腹の所見だけにとらわれず、その根本原因となっている筋肉の緊張や自律神経の乱れに対して、全身的にアプローチを行います。
鍼灸師は、まず全身の状態を診察し、胸脇苦満の程度を確認します。 前述の通り、胸脇苦満と関連が深いとされる背中の「棘下筋」の緊張やしこりに対して、鍼で直接アプローチして緩めます。 同時にお腹側の緊張している筋肉(腹直筋など)や、横隔膜の緊張を緩和するツボにも施術を行います。
さらに、ストレスによる自律神経の乱れ(肝気鬱結など)を整える目的で、手足や背中にある経絡上のツボにも鍼やお灸を使って施術を行います。 院によっては、鍼に微弱な電流を流す「電気鍼療法(パルス)」などを用いて、より深層部の筋肉のコリを効率よくほぐし、血流を促進させる方法を取り入れているところもあります。
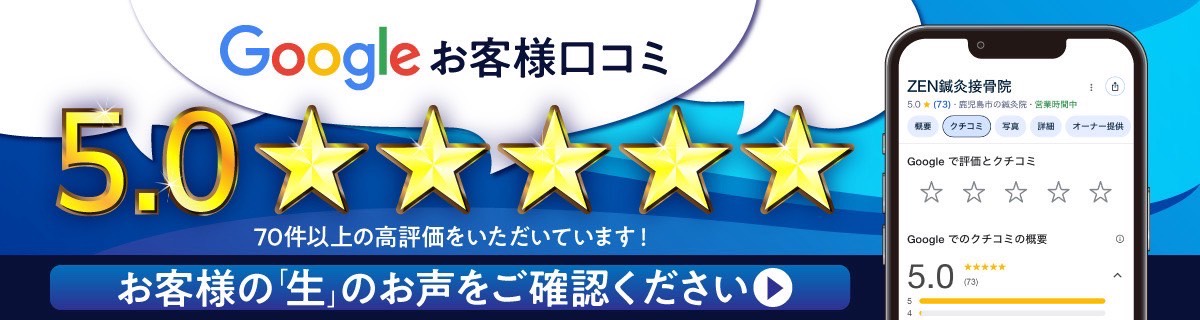


「眠れない夜を、もう終わりにしませんか。」
かつて私自身、過労とストレスで眠れない日々を過ごしました。
疲れているのに眠れない、朝はだるく気力も出ない…。そのつらさを経験したからこそ、同じように不眠症でお悩みの方の改善をお手伝いしたいと思い、この道を志しました。
鹿児島にある当院では、自律神経の調整×WHO(世界保健機関)でも認められている不眠のツボ×睡眠習慣の指導による不眠症根本改善を目的とした鍼灸施術を提供しています。
不眠症の背景にある自律神経の乱れやホルモンバランス、日常のストレスを丁寧に整え、自然に眠れる力を呼び起こし心と体を本来のリズムへ導きます。
■資格・実績
・国家資格4種(鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)
・睡眠の専門資格(日本睡眠機構 睡眠検定1級・スリーププランナー)
・10年以上の臨床実績/Googleクチコミ評価5.0(満点)
眠れない夜を重ねている方へ。
鹿児島で不眠症改善をめざす鍼灸院として、安心してお任せいただける環境をご用意しています。
「また自然に眠れる毎日」を、一緒に取り戻しましょう。